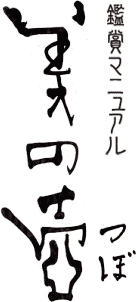file159 「青森のBORO(ぼろ)」
 |
青森の人々が何十年も、何百年もかけて使い続けてきた衣類をBOROといいます。 |
 |
野良着から肌着、そして寝具まで。すり切れ、ツギハギされたBOROは、青森では恥ずかしいものとされ、決して表舞台に出ることがありませんでした。 |
 |
消え行くBOROに関心を持ち、調査収集を続けてきた民具研究家の田中忠三郎さんにBOROと出会った頃のお話を伺いました。 忠三郎 「私が出会った時は、BOROという思いがしませんでしたね。ああ、こんなに布きれを大事にして、粗末にしないで、いのちあるものとして大事にツギハギしたんだなと。感激しましたね。涙が出ましたよ。こんなにモノを大事にする人たちがね、この雪国、青森にいたんだと」 |
 |
以来、青森県内の村々を歩き回り、40年間で集めた古い衣類は3000点以上に上ります。 |
壱のツボ 藍(あい)の濃淡を味わう

|
目の粗い麻布ゆえに寒さをしのぐ重ねの技がBORO独特の色合いを生み出しました。 |
 |
これはドンジャと呼ばれる掛け布団。 |
 |
冬場、このドンジャに家族みんながまる裸になり、ひとつにくるまって寝ました。 |
弐のツボ 布を重ねるは刺し子の技
 |
刺し子とは麻布を木綿の糸で刺し通し、つづっていく技です。青森では江戸の末期、刺し子の着物が作られるようになります。貴重な木綿糸の白色は麻布の藍の色に映え、女性たちのおしゃれ心をくすぐりました。 |
 |
忠三郎さんは、当時の女性達の生活について言います。 忠三郎 「麻布というのは目が粗いもんですから冬は寒いんですよ、ですから木綿糸が手に入るようになった娘さんたちが一生懸命刺しつづったんです。娘さんたちは5・6歳になりますと、針と糸を持たせて練習させて、15・6歳になりますと一人前の刺し手になって、きれいな模様の着物を作って、お嫁さんに行くときに2・3枚持っていくんですよ」 |
 |
二つ目のツボは、 |
 |
風呂敷包みから現れた数え切れないほどの古い小布。 |
 |
BOROの美しさ。 |
参のツボ BOROがいのちをはぐくむ
 |
BOROと同じように青森で古くから伝わる、もうひとつの布をよみがえらせる技。引き裂いた布を糸代わりにして織ることから、裂織(サキオリ)と呼ばれます。 |
 |
使い古し、これ以上使えなくなったボロ布(きれ)を青森の女性たちは捨てることなく、ふたたび布によみがえらせる技を編み出しました。 |
 |
さまざまな色合いの布が織り込まれるサキオリは朝焼けや夕焼けを思わせる見事なグラデーションを生み出します。 |
 |
忠三郎さんは、サキオリの色彩について 忠三郎 「日常的に憧れの太陽の明るさとか、光を求めていたものだと思いますよね。要するに明るさっていうのは、雪国にとって一番欲しいものなんです。ですから明るさを求めたのが、このカラフルなサキオリになっているんだと思いますね」 と言います。青森の人々は布そのものにいのちの息吹を感じ取っていたのかもしれません。 |
 |
これまで凶作や飢きんに、たびたび苦しめられてきた青森の人々。犠牲になった多くは幼い子どもたちでした。青森には、そうした子どもたちの霊を弔う地蔵がたくさん祭られています。 |
 |
毎年、新しい色鮮やかな衣装を地蔵に着せることで、青森の人々は、幼くして亡くなった子どもたちを代々慰めてきました。 |
 |
ボドコはBOROのなかでも異彩を放っています。 |
 |
ボドコの歳月はそれを使ってきた家族の歳月と重なっていきました。 |
 |
寒さと戦い、生き抜いてきた青森の人々。 |
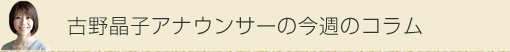
大切に使い込まれてきたモノが放つ“美しさ”にハッとさせられました。
“ボロ”というと、古くて汚れたものだという先入観があったのですが、“BORO”は違いました。何度も継ぎはぎされ、人の汗や涙がしみ込み、そこには新しいものには出しきれない独特の味わいが生まれていたのです。モノがあふれ、古くなったら新しいものに換えればよいという現代のわたしたちに“BORO”は一つのアンチテーゼを示しているようにも感じました。
共に藍色で染めてあるからかもしれませんが、青森で生まれた“BORO”を眺めていると、海外で誕生した“ジーンズ”と似ているように思いました。ジーンズも使い込むほどに味が出てくる服ですよね?!特にダメージ加工されたジーンズは履き古したような色あせや傷こそが魅力の一つとされています。中には新しいものにわざと傷をつけたり、破いたりしているものもあるそうです。そう考えると、使い古された感じのものを好むという文化は日本でも海外でも通ずるものがあるのではないでしょうか?
今週の音楽
| 楽曲名 | アーティスト名 |
|---|---|
| First Song | Charlie Haden / Pat Metheny |
| It Never Entered My Mind | Miles Davis |
| Cinema Paradiso | Charlie Haden / Pat Metheny |
| When I Fall In Love | Miles Davis |
| He's Gone Away | Charlie Haden / Pat Metheny |
| One Quiet Night | Pat Metheny |
| North To South, East To West | Pat Metheny |
| Spiritual | Charlie Haden / Pat Metheny |