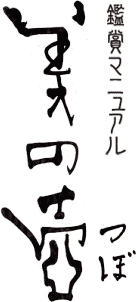file158 「百貨店」
 |
平成21年、国の重要文化財に指定された髙島屋東京店。 |
 |
天井にはしっくいが塗りこめられ、柱をイタリア産の大理石で覆い尽くしたぜいたくなものです。 |
壱のツボ 玄関はモダン都市の顔
 |
鉄筋コンクリート造りの重厚な建物も、空へと視線を導くことで軽やかに見せています。 |

|
石の壁と金属の外灯。異質な要素のぶつかり合いが、緊張感あふれる造形美を生み出しています。 |
 |
日本で最初にできた百貨店、東京・日本橋の三越です。 |
 |
三越は、江戸時代から続く老舗(しにせ)の呉服店でした。 |
 |
三越の永森昭紀さんです。 永森 「玄関は震災と戦災と二度焼けました。ただなるべくもとの形ということで、そのつど復元をしています。日本橋は歴史のある町ですから、街の人が『おまえ三越は変わっちゃダメだろ』という部分がかなり強いんです」 三越が百貨店として成功を収めたことで、町もともに繁栄するようになり、ライオンは、日本橋の顔として愛され続けてきました。 |
 |
こちらは大阪の街の顔。 |
弐のツボ ワンダーランドへいざなう多国籍装飾
 |
国の重要文化財、東京・日本橋の髙島屋。 |
 |
柱頭には、寺院建築に用いる肘木(ひじき)の形に作られています。 |
 |
きらびやかな百貨店の内装の中でも、極めつけとされるのが、大阪・心斎橋の大丸の装飾です。 |
 |
扉の上のステンドグラスに描かれているのはイソップのぐう話。 |
 |
店内を埋め尽くす幾何学模様。 |
 |
1階のエレベーターホールは、西洋風とイスラムのアラベスクが混ざり合った様なデザインで、遊び心が感じられます。 |
参のツボ 窓越しに楽しむ季節の物語
 |
百貨店が一日で最も美しい、夕闇迫るころ。 |
 |
日本に百貨店が誕生した時からあったショーウインドー。 |
 |
クリスマスの夜、店が終ると同時に展示の入れ替えが始まりました。 |
 |
奥行き1メートル程の空間に運び込まれる正月用のオブジェ。 |
 |
完成したのは、松竹梅の生花を用いた和の空間。 |
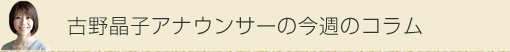
みなさんにとって「百貨店」とはどんなところですか?私にとっては意外なものがみつかるところ。というのも幼いころ、百貨店で“あるもの”を拾ったからなのです。
お盆のころ、母方の祖父母を訪ねて鹿児島へ里帰りし、百貨店へ買い物に行ったときのこと。大人たちが商品を選んでいる間、私は店内のお気に入りの場所で妹と遊んでいました。そこは美しい曲線からなる柱や梁(はり)に囲まれた、お城の中にあるような踊り場。自分がお姫さまになったような気分に浸っていたとき、目に止まったのが、黒く光る小さな物体。柱の隅で動かないそれをよく見てみると・・・、そこにいたのは、なんと小さな“オスのコクワガタ”でした!!どこからか入ってきて出られなくなっていたようです。私はその虫を持ち帰り、飼うことにしました。母と飼いかたを調べ、マメに面倒をみたことを今でも覚えています。百貨店で出合ったそのコクワガタは私の虫嫌いを克服させ、貴重な思い出も残してくれたのでした。
このコクワガタにはもうひとつエピソードがあります。連れ帰った自宅で、一度、失踪事件を起こしたことがあるのです。虫かごの扉が少し開いていて、そこから逃げてしまったのでした。家の周りは木々に囲まれていたため、外の方が幸せになれるという母の言葉になだめられ、泣きじゃくるのをやめた、一か月後・・・。なんとメスを連れて二匹で家へ戻ってきたのです!家族みなで驚いたことは言うまでもありません。
今週の音楽
| 楽曲名 | アーティスト名 |
|---|---|
| Rhapsody in blue | プレヴィン指揮ロンドン交響楽団 |
| sing sing sing | Benny Goodman Orchestra |
| Overture | Windmill Theatre Band |
| Overture (from Chicago) | Derrick Watkins |
| On the trail | Itzhak Perlman , Oscar Peterson |
| Boogablues | Gerald Clayton |
| Black and Tan Fantasy | Duke Ellington and His Orchestra |
| Letting in the sunshine | Will Young |
| Unzulänglichkeit ~from “ThreePenny Opera” | André Previn & J.J.Johnson |
| Oh, lady be good | Zubin Metha (cond) Gary Graffman (Apf) New York Philharmonic |
| As time goes by | Claude Williamson |
| When day is done | Coleman Hawkins |
| Yo vivo enamorao | Jan Lundgren trio |
| Oh, Kay! | Michael Tilson Thomas (cond) Buffalo Philharmonic |
| Moon River | Henry Mancini |
| Just Friends | Charlie Parker with strings |
| Night and day | Steve Tyrell |