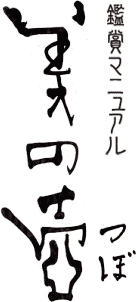file152 「武将ファッション」
 |
今、戦国時代があついブームを呼んでいます。 |
 |
それを象徴するのが個性的なファッョンです。 |
 |
ファッションデザイナー、山本寛斎さん。 山本 「本来の日本人は、ふだんからすごくきれいなものをよしとする、目立つことをよしとする。それをかぶくという、歌舞伎という単語ができたくらい。安土桃山文化を見るとその水準なんですよね」 戦国武将たちのファッションセンスには、世界的なデザイナーをもうならせる驚きが詰まっているのです。 |
壱のツボ 立てものに武将の心意気あり

|
まずは、兜に注目です。 |
 |
国宝など文化財に指定された鎧兜の修復を手がけてきた甲冑師(かっちゅうし)の、森崎干城さん。 森崎 「戦国時代は死との背中合わせ、身を守るだけでなく、かっちゅうは、死に装束ともなります。自分の思い入れもかなり入っているので、威厳と風格だけではなく、信仰や大切なものが盛り込まれています。」 |
 |
武将の思い入れが凝縮している場所、それが、たてものと呼ばれる兜の飾りです。 |
 |
脇には鹿の角をかたどった立て物。神の力が宿るとされていました。 武将ファッション、最初のツボは、 |
 |
木の棒に熊の毛を張り付けた、この立て物は、毛虫を表しています。 |
 |
やがて、立てものが鉢の部分と一体化した「変わり兜」が生まれました。 |
 |
こちらも変わり兜。 |
 |
そして、この一の谷兜とゆかりが深いのが、「大水牛脇立て兜」。 |
弐のツボ オシャレ合戦は南蛮モードで
 |
今度は鎧の上にまとう陣羽織のお話です。 二つ目のツボは、 |
 |
こちらも、羊毛でできた陣羽織。 |
 |
そこには、おしゃれを越えたある意図があったと、静岡大学名誉教授(戦国史)の小和田哲男さんは言います。 小和田 「ヨーロッパからいろんな、たとえばビロードだとか、輸入して。経済力がないとできない財力を誇示する意味もあって、おまえらには着れないだろう、大将としての一種のステータスシンボルという側面もありますね」 |
 |
続いては、戦国のファッションリーダーと言われる、伊達政宗の陣羽織。 |
参のツボ 見た目で脅す、鎧(よろい)の力
 |
岐阜県の関ヶ原では、毎年、合戦祭りが開かれ、甲冑(かっちゅう)姿の人々でにぎわいます。 小和田 「単なる防具と言うより、戦国たけなわになると、相手を威圧するとか、ビックリさせるものがあらわれるようになる」 三つ目のツボは、 |
 |
徳川四天王といわれ、勇猛な戦いぶりで知られた井伊家に伝わる鎧。 |
 |
関ヶ原の合戦を描いたびょうぶ。 |
 |
末永 「成人女性に今の気分を表現してもらったものすごい赤、夫婦げんかの後、戦闘モードだった。強い赤は攻撃的な感じ。赤は人間の 一番極限の血の色。その色に死の危険を感じ取った。向こうからやってきたら、火の大群のような恐怖やショックを与える効果があったでしょう」 この赤は戦場での心理を計算したものだったのです。 |
 |
異様な出で立ち。 |
 |
最後は人の心理を突いた鎧です。 |
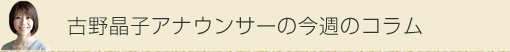
“歴女(れきじょ)”という言葉をご存知ですか?戦国時代の武将や歴史を愛する女性たちのことを言うのだそうです。戦に出れば生きるか死ぬかの過酷な世。そんな時代を走りぬけた武将たちの鮮烈な生きざまが女性達をひきつけているのだとか。
歴女を名乗るのはおこがましいですが、私も“お城”となると無性にワクワクします!旅先でお城があれば必ず訪れています。最初は遠くから石垣や城の姿をじっくりながめます。中へ入ったらその城にまつわる資料を読みこみ、当時使われていた器や調度品を丁寧に見て、気持ちを盛り上げていきます。そして最後に急な階段を登っていくと・・・そこに広がるのは眼下に見下ろす、天守からの眺め!まるで自分が城主になったような気持ちになります。「○○はどんな気持ちでこの景色を見ていたのだろうか?」なぁ~んて、勝手に思いをはせています。最後にお茶屋さんでお団子と抹茶をいただいて、“家紋”付きの土産品を探す。これが私の城の楽しみ方です。
今週の音楽
| 楽曲名 | アーティスト名 |
|---|---|
| Doug 's Minor B'OK | Hank Mobley |
| 7 | Miles Davis & Gil Evans |
| Three Bags Full | Herbie Hancock |
| Shout ' Em Aunt Tillie | Marcus Roberts |
| Twelve Inch | Curtis Fuller |
| Senor Mouse | Turtle Island String Quartet |
| 3 | Miles Davis & Gil Evans |
| Indian Song | Wayne Shorter |
| I Remember Clifford | Lee Morgan |
| Stella By Starlight | Horace Parlan |
| Just Friends | Charlie Parker |
| Stardust | Clifford Brown |
| 5 | Miles Davis & Gil Evans |
| A Night In Tunisia | Turtle Island String Quartet |
| Decline | Turtle Island String Quartet |
| Clara | Duke Peason |