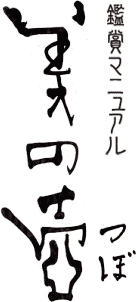File143 「クラシックカメラ」
 |
東京渋谷にある美容院。クラシックカメラが、暖かみのある雰囲気を醸し出し、店を訪れる若い女性にも人気です。 |
 |
クラシックカメラの定義はさまざまですが、一般的に1960年代ころまでに製造された機械式のカメラのことを言います。 |
壱のツボ 手と一体化するかたち
 |
丸みのあるボディの上に丸い操作ダイヤル並ぶ、私たちに一番なじみの深いカメラの形。 |
 |
カメラが誕生したのは、今から170年前のこと。 |
 |
そんな中一人の技術者がカメラの歴史に革命を起こします。 |
 |
そこでバルナックが着目したのが映画に用いるセルロイド製のフィルムでした。 ガラス乾板が主流だった当時のカメラにセルロイド製フィルムを効果的に用いる方法を確立し、カメラを小型化しました。 |
 |
曲線が生む優雅なかたち。 |
弐のツボ 名玉レンズに豊かな個性あり
 |
カメラのレンズには、被写体に応じたさまざまな種類のものがあります。 |
 |
飯田 「適材適所言うこともありますけどね。どんなところでも無難にこなす人ばっかしでは困ると思うんですね。レンズもそうだと思います。ですからちゃんと写ることは当然良いことなんですけど、ちょっとおもしろい癖を持ってたりするレンズって言うのはやっぱり使いたくなるかなと思いますね」 まるで人間のように一枚一枚が違うクラシックレンズ。 二つ目のツボは、 |
 |
クラシックレンズの個性とはどのようなものなのでしょうか。 |
 |
明るさのバランスに特徴があるレンズでは周辺にいくほど暗くなり、視線を花へと導きます。 |
 |
レンズ研磨職人の山崎さんは、傷や汚れが付いたレンズを磨き、今も名玉レンズの個性を大切に守り続けています。 山崎 「レンズはただシャープネスだけを追っかけるんじゃなくて、もっと個性と言いますか、自己主張的な物があって良いと思ってるんですよ、私は。そういう物は現行機には感じられないけど、クラシック系のレンズにはすごくそういう物がたくさんあります。それがクラシックレンズの魅力ですね」 |
 |
レンズの個性が生む深い味わい。 |
参のツボ ボディに纏(まと)った先端モードを楽しむ
 |
クラシックカメラのデザインには最先端の流行が取り入れられています。 |
 |
それまで装飾など施されていなかった箱形カメラも、アール・デコの時代、華やかに生まれ変わりました。デザインの世紀と言われた20世紀が、本格的に幕を開けたのです。 |
 |
1930年代には、流線型のデザインが流行ります。 高島 「こちらは1936年のバンタム・スペシャルというカメラなんですが、開けると中は蛇腹の古いカメラなんですが、それをカメラで流線型にした物です。カメラが風を切り裂いて走ると言うことはありませんけど、やはり時代の影響を受けたと言うことだと思います」 |
 |
20世紀半ば、大量消費時代を迎えたアメリカで、新しい発想によるカメラが登場します。ガレージのシャッターのようなカバーが特徴のアンスコフレックスです。 |
 |
このカメラをデザインしたのは、20世紀を代表する工業デザイナー、レイモンド・ローウィ。 ローウィは機能優先で武骨だった工業製品を、おしゃれで思わず欲しくなる形にデザインし直しました。 |
 |
ローウィは時代の流行をカメラのデザインに取り入れざん新なアイデアを考え出しました。 |
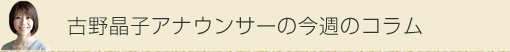
亡き祖父はカメラが大好きで、どこへ行くにも必ず持っていく人でした。私や妹、いとこ達を遊園地や旅行に連れていっては看板の前でパチリ、噴水の前でもパチリ。あまりに何度もポーズをとらされるので、妹はぐずり出し、いとこはすねてニコリともしないように・・・。私はというと、大声で泣きじゃくる妹としかめっ面のいとこに挟まれ、下ばかり見つめていました。通行人からのまなざしが気になって恥ずかしかったのです。祖父はそんな私たちのことはお構いなしに「ハイ、チーズ」と1人だけ笑顔でシャッターを切っていたものです。
それから20年あまり。アルバムには祖父が撮ってくれたあの時の写真が残っています。頬を真っ赤にして泣いている妹、つむじが見えるほど下を向いている私、カメラを見ずに横を向いているいとこの姿。祖父がカメラのレンズを通して見ていた光景がそこにありました。改めて見てみると、そんな風に3人がそっぽを向いているシーンだからこそ、そのときの気持ちが手にとるように分かる・・・。祖父が笑いながら撮影していた訳が理解できたような気がしました。フィルムカメラはシャッターを押した時の一瞬が勝負。いま主流のデジタルカメラは撮り直しがききますから、もしかしたらあの写真は撮れていなかったかも?!しれません。“今”を意識して撮ったからこその一枚なのだとしみじみ思います。
アルバムをめくっても祖父が写っている姿はほとんど無いのですが、残された写真を眺めていると、祖父がカメラを通して注いでくれた愛情をしっかり感じることができるのです。
今週の音楽
| 楽曲名 | アーティスト名 |
|---|---|
| Manege | Francois Rauber |
| Falling in Love With Love | Helen Merrill |
| Bag's Groove | Horace Parlan |
| Milestones | Turtle Island String Quartet |
| NOS.14 | Chick Corea |
| Seven Steps to Heaven | Miles Davis |
| Autumn Leaves | Cannonball Adderley |
| Tournee Rapide | Jean Yavote |
| O Grande Amor | Gary Burton & Makoto Ozone |
| Green Sleeves | Paul Desmond |
| NOS.15 | Chick Corea |
| Moon Love | Chet Baker |
| Just Friends | Charlie Parker |
| A Night? In Tunisia | Turtle Island String Quartet |
| A Powdered Wig | Henry Mancini |
| Fly Me to The Moon | Frank Sinatra |
| Chanson des Forains | Jean Yavote |