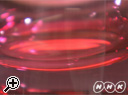|
明治から昭和初期に日本で作られたガラス。
西洋から近代的なガラスの製造技術が入ってくると、当時の職人たちは懸命にその技を学びました。
|

|
文様を見てみると、松の葉や青海波(せいがいは)と呼ばれる波が使われています。
いずれも日本の伝統的な文様です。 |

|
ガラスは当時の人々にとって、あこがれの品。
和のテイストをもったモダンな作品が次々と登場しました。
こちらはおぜんやおわん、はしに至るまですべて霜が降りたような模様が特徴の結霜(けっそう)ガラスと呼ばれるもので作られています。
|

| 日本の食卓に欠かせないしょうゆさし。
|
 |
厚みのある質感に「波に千鳥」の文様が浮かび上がっています。
1点1点職人たちがこだわりをもって作り上げたガラスの器。
西洋のものを日本独自にアレンジし身近な芸術品です。
|
 |
現在、女性の人気を集めているガラスの器があります。
大正時代に作られていたものを復刻しました。 |
 |
こちらは大正から昭和にかけて、盛んに作られた乳白色の器です。
白いレースのようなはかないぼかしがさまざまな文様を浮かび上がらせます。 |

|
竹久夢二伊香保記念館館長 木暮享さん。
木暮「これこそ日本の色、大正の色落ち着いた色を出す日本の感性。あからさまに見せないところが想像させる」
ガラスの器一つめのツボは、
「ぼかしが想像をかきたてる」 |
 |
このぼかしは、「あぶり出し」という技法によるもの。
「あぶりだし」とは、温度差により、文様を浮かび上がらせる技法です。ガラスの原料に「骨灰(こっぱい)」と呼ばれる牛の骨の粉を混ぜます。これを混ぜたガラスを急激に熱すると乳白色になります。
|

|
模様を作るには、凹凸のついた型にいれ、空気を吹き込みます。
型の中でガラスをふくらませると凹凸ができ、温度差が生まれます。
|

|
このガラスを再び熱すると、ガラスのへこんだ部分だけ温度が急激に上昇し、乳白色になるのです。
|
 |
そもそも「あぶりだし」は、ヨーロッパの技術。
ヨーロッパのものはガラスの表面がでこぼこしています。
|
 |
それに対し、表面が滑らか。
最後に再び型にいれ、空気を吹き込むからです。
こうすることで、溶け合うようなぼかし文様が生まれます。
木暮「毎日日常、朝から晩まで自然から受け取るかたち、そこにデザインを生み出す日本人の優れた感性。生活の中に自然を取り入れ、生活を楽しんだ日本人はそれをガラスのなかにも取り込んだんです」
乳白ぼかしのガラスにわずかな色を加えることで、想像がぐっと広がります。
日本で作られてきた、ガラスの器にはたおやかな自然の表情が溶け込んでいるのです。 |