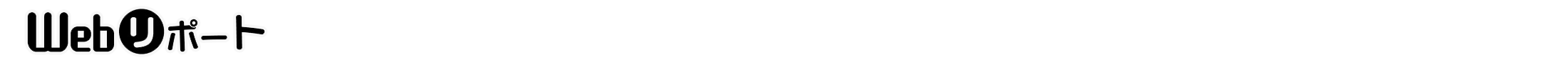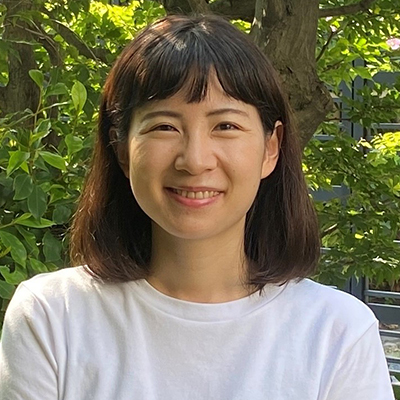“感覚過敏を知ってほしい”16歳・加藤路瑛さんの挑戦
- 2022年11月30日

教室のざわざわした音で頭が痛くなる。
服の縫い目やタグが痛くて着られない。
食べられるものが極端に限られる…。
幼いころからこんな症状に悩んできた人がいます。加藤路瑛(じえい)さん、16歳。加藤さんの悩みの正体は、「感覚過敏」だといいます。聴覚や味覚など五感に敏感に反応し、日常生活に困難を抱える状態のことです。
感覚過敏が原因で、学校生活を送ることが難しくなるなどつらい過去も経験してきた加藤さん。自身の体験をつづった著書を出版したり、刺激の少ない洋服を開発したりするなど精力的に活動をしています。
周りからは見えづらい感覚過敏。加藤さんはどのように向き合い、どんな思いで活動を続けているのでしょうか。
(首都圏局/ディレクター 大岩万意)
食べることがつらい…幼いころの葛藤

加藤さん(右)と母・咲都美さん
加藤さんは、幼いころから人とは感覚が違うことに悩まされてきました。
しかし、それが「感覚過敏によるもの」と自覚するまでには、時間がかかったそうです。
加藤さんにとって特につらかったのが、食事の時間です。食べられるものが極端に限られ、食べ物によっては体に不調をきたすほど、敏感に反応するそうです。

加藤路瑛さん
「例えば、しょうゆ味の濃いものを食べると頭痛がしたり、オレンジジュースを飲むとのどが焼けたりするような感覚があります。ですが、白米など一定のものは食べられるんです。単なる好き嫌いと違うのは、吐き気や頭痛など体の不調として現れる点だと僕は考えています。幼いころは僕自身もこの感覚の正体がわからず、ごはんの時間はただただ苦痛でした」

小学生のころ、加藤さんのクラスでは、「苦手な物でも一口は食べる」というルールがありました。
しかし、その一口を食べる苦痛を想像すると手を付けることができず、昼休みも掃除の時間も、皿を見つめるだけだったといいます。
家でもとにかく食べない息子の様子を見て、母親の咲都美さんは、「自分の料理がおいしくないのか」「息子がわがままなのか」と悩み続けました。そのときの心境を、ことし出版された加藤さんの著書の中で振り返っています。

【著書引用】(母・咲都美さん)
いろいろ工夫して野菜を小さくしたり、キャラ弁にしたり。それでも、息子は食べてくれない。『食べないと大きくなれないよ』と嫌がる息子の口に食べ物がのったスプーンを無理やり入れたことは数え切れません。
疲れていてもがんばってつくった食事をひと口も食べなかったとき、何度怒鳴ったことでしょう。
(中略)
もう1つ、後悔があります。息子は幼稚園時代から、『しまじろう』というキャラクターのフォークとスプーンで食事をしていました。
ある日、しまじろうのシールが取れてしまって、ただの銀色のスプーンになってしまったのです。
そのスプーンを見て悲しそうにする息子を前に私は、『路瑛がごはん食べないから、しまじろうは悲しくなってどこかに行ってしまったね』と言い放ってしまったのです。
息子は声を出さずに涙をポロポロとこぼして、静かに泣いていました。
(加藤路瑛著「感覚過敏の僕が感じる世界」より)

キャラクターのシールがはがれたカトラリー
感覚過敏が原因で不登校に…
実は、給食の時間に限らず、学校生活のあらゆる場面で、加藤さんは苦痛を感じていました。
・休み時間など、教室の騒がしい音で頭が痛くなった
・いろいろな弁当のにおいが充満した教室が耐えられず、周囲から離れてひとりで食べていた(中学校)
・ブレザーなど制服が重く感じ、生地が肌にあたる感触がチクチクと痛く感じた(中学校)
こうした悩みが続き、加藤さんは中学1年生になると、教室から逃れるように保健室に通うようになりました。
そこで、保健室の先生から「それって、感覚過敏なんじゃない?」と教えてもらったといいます。
感覚過敏とは
五感などの諸感覚が過敏になっていて日常生活に困難さがある状態をいいます。
感覚過敏は、病名ではなく症状です。そのため、診断名があるわけでもなく、治療方法があるわけでもありません。
感覚過敏は発達障害の人に多く見られる症状です。
ほかにも、自律神経失調症、うつ病やPTSDなどの精神疾患などでも感覚過敏の症状は見られます。
加藤路瑛著「感覚過敏の僕が感じる世界」(兵庫教育大学・小川修史准教授 監修)参照

中学1年生の時、初めて感覚過敏ということばを知った時は、目の前が明るくなるような気持ちだったと加藤さんは語ります。
加藤路瑛さん
「苦手なものが多かったり、すぐに体調が悪くなったりする自分は『弱い人間』なんだと思っていました。だから、僕が弱いのではなく、感覚過敏が僕を弱くしていたんだと気づいた時は、ほっとしました」
とはいえ、学校での困りごとはなかなか解決しませんでした。保健室に通う日々が続き、中学1年生の3学期には不登校となります。
そして、翌年退学し、フリースクールに通い始めます。そこには厳しい校則もなく、「一人ひとり違うのが当たり前」という雰囲気があったそうです。
「ひとりでお弁当を食べる人がいたり、休み時間も好きなように過ごしたり、とにかく自由でした。自分に合った環境やペースで学校生活が送れるようになり、ストレスから解放されました」
その後加藤さんは、自身の困りごとと向き合い、自分なりに解消する方法を身につけてきました。
・外食は極力せず、食べられるものを食べる。
・周囲の音を聞こえにくくするため、ノイズキャンセリングイヤホンを身につける。
・まぶしさを抑える調光レンズの眼鏡をかける。
・自分が着られる服を見つけたら、同じ物をローテーションして身につける。
環境を変えたことや、こうした対策を編み出したことで、以前よりストレスが減り、過ごしやすくなったそうです。
母・咲都美さんも、「感覚過敏」ということばに出会い、ありのままの加藤さんを受け入れられるようになっていったといいます。
母・咲都美さん
「感覚過敏ということばを知らなかったときは、息子のいっけん神経質に見えるところやわがままに見えるところが、親にとってはかなりのストレスでした。『自分の子育てのしかたが悪いんじゃないか』、『息子自身の問題なのではないか』など、いろんなことを悩んでいました。感覚過敏ということばを知り、『自分や息子が悪かったわけではなかったんだ』と、肩の荷が下りたような気持ちがありました。
退学し“ふつう”とは違う道を進むことについては、息子の未来が予測できないという不安も感じていました。それでもフリースクールには、同じ感覚過敏のある子など多様な生徒が集まっていて、自由な環境に驚きました。そのような環境に身を置くようになって、息子ものびのびと過ごせるようになったんです」

「感覚過敏の課題を解決したい」13歳で事業をスタート
中学生のとき、「感覚過敏」ということばを知った加藤さん。SNSで「感覚過敏で困っている人いませんか?」と呼びかけると、同じ症状で悩む多くの人から反応がありました。「困っているのは自分だけではない」と確信します。
そこで、なんと13歳で「感覚過敏研究所」という事業を立ち上げます。
目指すのは、「感覚過敏の課題を解決すること」。学業のかたわら、「社長」として活動を始めます。

感覚過敏研究所のサイト画面
感覚過敏を周囲に知らせるグッズの開発
まず行ったのは、周囲に理解を広めるためのグッズの開発です。
例えば、写真(下)の缶バッチ。過敏さを周囲にさりげなく伝えることができるようにと作りました。かわいらしいイラストとともに「苦手な音があります」「マスクがつけられません」などメッセージが書かれています。
感覚過敏は目に見えない困りごとだからこそ、こうしたグッズを活用し周囲に伝えるきっかけになればと加藤さんは考えています。

刺激の少ないグッズの開発
さらに、感覚への刺激が少ないグッズの開発にも力を入れています。
ことし3月に立ち上げたのは、アパレルブランド。肌への刺激が少なく、着心地のよい服をコンセプトにしています。
加藤さん自身、「服が痛い」と感じることが多く、着られる服がなく困っていたことがきっかけでした。ブランドでは生地選びからデザインまで、加藤さん自ら試着を繰り返しながら、製造を行っています。

実際に販売しているパーカ、その特徴はというと…。
ふつうの服に付いている首元のタグはありません。タグがあるとチクチクと痛く感じるからだそうです。
さらに、縫い目が肌にあたるのも痛みの原因でした。そこで、縫い目を外側に出しました。外側の縫い目はピンクのラインになっていて、デザインとして楽しめるようになっています。
また、リュックを背負ったときなどに、リュックの肩ひもの下にパーカの縫い目のラインがあたると不快感の原因になるため、縫い目を肩から少しずらして重ならないようにしたそうです。

商品は主にオンラインで販売していますが、半年間で200着以上と予想を超える多くの注文が来たそうです。感覚過敏の症状に悩む人や家族からは、「着心地が良い」「こういう服を探していた」といった声が寄せられているといいます。
悩む人たちが交流できる場づくり
さらに加藤さんは、感覚過敏の症状で悩む人どうしの交流を大切にしてきました。というのも、感覚過敏がまだ広く知られていないため、「困りごとを周囲に打ち明けられない」と、一人で悩んでいる人が多くいることに気づいたからです。
そこで立ち上げたのは、オンラインコミュニティーです。
感覚の過敏さで悩む人やその家族が、無料で参加できます。
立ち上げからメンバーの数は増え続け、2年半で600人以上となり、年齢層も10代から60代とさまざまです。
メンバーはチャットを通じて、感覚過敏の困りごとや、解決するための工夫やアイデアを共有しています。
加藤さんが希望の光に 当事者や家族の声
加藤さんの存在が精神的な支えになってきたという人がいます。
静岡県に住むヨウコさん(仮名)。高校1年生の息子・ダイキさん(仮名)が、幼いころから感覚が敏感なことに悩んできました。
静岡県在住 ヨウコさん(仮名)
「息子は小学校に入学すると、家に帰るなり玄関でどっと倒れ込むほど疲れ切っていました。理由を聞くと、『教室の音が騒がしくて疲れてしまう』と話していました。また、登下校中はいつも帽子を深くかぶりうつむいて歩いていたんですね。その様子を見て私は、『そんな暗い子に誰も話しかけたいなんて思わない。上を向いて明るくしていないと友達ができないよ』と言ったんです。当時は、事情を知らずに言ってしまいました。『太陽の光がまぶしかったんだよ』と数年後に息子から聞いて、初めて理解したんです。傷つけるようなことばをかけてしまったと、今では後悔しています」
ダイキさんの悩みの正体を知りたいと医療機関を受診しましたが、「特に問題はない」と診断には至りませんでした。手がかりを求めてインターネットなどで調べるうちに、「感覚過敏」ということばを見つけたヨウコさん。息子はその当事者だと確信するようになりました。
ダイキさんは中学校に上がっても、教室の音や通学時の電車の音などを苦痛に感じ、疲労が蓄積していきました。
そしてとうとう、中学2年生の時に「もう学校ムリだ」と漏らしたそうです。

息子がみんなと同じ“ふつう”の道を歩めないかもしれないということに、葛藤もあったというヨウコさん。しかし、「このままでは息子はうつになる。息子にあった環境を見つけなければ」と気持ちを切り替えることができました。
それは、加藤路瑛さんの体験記を読んだからです。
「加藤さんも、感覚過敏のためにふつうの学校に通えなくなるなど、息子と同じ経験をしている。それなのに、とても前向きに自分のやりたいことをやっている。その姿に感動して、私にとっては“希望の光”になったんです」
加藤さんのように、環境を変えれば、息子も変わるのではないか…。
そう考えたヨウコさんはダイキさんと話し合い、通信制の高校に進学させることにしました。さらに、ダイキさんの好きなことを大事にしたいと、プログラミングの専門学校にも通うことに。
それぞれの学校にかけあい、周囲の音を聞こえにくくするノイズキャンセリングイヤホンや、まぶしさを軽減する調光レンズの眼鏡の使用を認めてもらいました。
「環境が変わったことで息子は人が変わったように明るくなり、夢に向かって歩みだしています。加藤さんには、親子で救われています」
いまではダイキさんも加藤さんの主宰するオンラインコミュニティーに参加するなど、自分自身の特性に向き合うようになったそうです。
「感覚過敏でも生きやすく」挑戦を続ける社長
学業のかたわら、絶えず新しいことに挑む加藤さん。これからの目標を聞いてみました。

母・咲都美さんと商品をチェックする加藤さん
加藤路瑛さん
「目標は、感覚過敏の困りごとをなくし、感覚過敏があっても生きやすい社会を作ること。そのために、感覚をコントロールできるようなテクノロジーの研究・開発を行っていきたい」
力強く答えてくれた加藤さん。もう一つの目標は「バイクの免許を取ること」と、高校生らしい素顔も見せてくれました。
感覚過敏かな?と思ったら…
実際に、自分や家族が「感覚過敏かな?」と思ったら、どうしたらよいのでしょうか。福岡市のクリニックで感覚の過敏さに悩む人たちの相談やケアを行っている、精神科医の黒川駿哉さんに聞きました。

精神科医・慶應義塾大学医学部 特任助教 黒川駿哉さん
精神科医・黒川駿哉さん
「相談先としては、発達外来や小児科、大人なら精神科が考えられます。医師は、ほかの特性が伴っていないか網羅的に診断するので、受診することで発達障害やその他の病気や障害と診断される可能性もあります。しかし、“感覚過敏で困っている”というだけでは病気の判定になりにくいのが現状です。
そこで大切なのは、欧米では広がりを見せている『ニューロダイバーシティ(神経多様性)』という考え方です。感覚は人それぞれ違い、感覚が鈍い人もいれば敏感な人もいる。病名が付かなくても、感覚過敏に悩む方はいます。このことを前提に、職場や学校など、社会全体で配慮をしていく必要があると思います」
それでは、例えば学校では、感覚過敏の生徒にどんな配慮ができるのでしょうか。
黒川さんに尋ねました。
「視覚が過敏な人の中には、視界に入った情報が一度に頭に入ってきてしまい混乱するという人もいます。そのため、ほかの生徒がたくさん前に座っている状態で黒板を見ても集中できない、黒板の隣にある掲示物の情報も入ってきてしまい、しんどいという方もいます。そういうときは、よけいな情報が目に入らないよう、一番前の席に座ってもらう、掲示物はブラインドなどで一時的に隠す、サングラスの使用を許可するといった対策が考えられます。
音に敏感な生徒には、耳栓やノイズキャンセリングイヤホン、イヤーマフなどの使用を許可することも考えられます」
そして黒川さんは、何より、つらかったら教室から離れる時間も大切だと話します。
「私がとても有効だと思っているのは、“しんどいときはいつでも抜けていいよ”というメッセージを発することです。日本の学校では、授業中はしっかり席に座っていることが美徳というか、重視されると思います。ですが、海外の学校では、気分が悪くなったら席を外す、外の空気を吸ってくる、というのはよくある光景です。感覚の過敏などでクラクラしたときなどに、先生と本人の間で合図(ジェスチャーなど)を決めておき、合意が取れれば教室の外の落ち着ける場所(図書室、保健室や特別支援教室など)に行き、戻ってくることができる。こういう環境を整えることは大切だと思います」
今回の取材で、私がお話を聞いた感覚が過敏だという人の中には、職場の理解を得ることができずに退職せざるを得なかったという方もいました。その方は、パソコンのキーワードを打つと我慢できないほど指先が痛いという症状があったそうです。
感覚過敏は「病気」とは診断されませんが、当事者にとっては日々つき合わなくてはいけないものです。感覚の違いを認める『ニューロダイバーシティ』の考え方が広がり、学校や仕事をあきらめなくてすむような社会になってほしいと強く思いました。