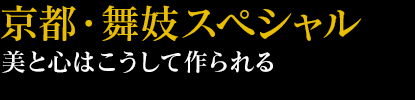舞妓が朝一番に向かう場所がある。舞妓専門の美容室だ。舞妓はカツラを用いず、地毛で髪を結うのが習わし。その髪型は、舞妓の重要な要素である「おぼこさ(幼く、かわいらしいこと)」を表現する上で欠かせない。しかも一度結うと、洗髪することなく、1週間はもたせないといけないため、その髪結いには熟練の技が求められる。
そんな舞妓の髪を結い続けて65年の髪結い師が芦田須美(83)だ。京都で5つある花街のひとつ、宮川町で最も多くの舞妓を顧客に抱える名人だ。
用いるのは、びんつけ油とこより。芦田には、油を極力使わないというこだわりがある。油を多くつければ髪はまとまりやすい一方で、髪結い後に舞妓が日々行う手入れは煩わしくなる。髪をただ結うだけではなく、舞妓のためになりたい、という芦田ならではの気配りだ。
しかも、その手は、まるで“意思”を持っているかのようにサッサと動き、舞妓の髪をあっという間に結い上げていく。舞妓の日本髪は、立体的で難しい造形にもかかわらず、やり直しは、ほとんどない。
「何も考えず結ってるんですけど、手が覚えてんのか、手が勝手に動いていきます。だいたい一発でいきますね。長年の“アレ”でしょうね。やっぱり一生懸命、結っているんです。」
舞妓を送り出すとき、芦田が決まってかける言葉がある。「いってらっしゃい。」これから始まる、舞妓の長い一日にエールを送るのだ。
![]()

![]()
 売れっ子の舞妓、とし恵美さんの髪を結う芦田さん
売れっ子の舞妓、とし恵美さんの髪を結う芦田さん
舞妓の着付けにも、いなくてはならないプロフェッショナルがいる。それは、男衆(おとこし)。舞妓と芸妓の着付けを行う人たちだ。舞妓は、通常の1.5倍も長い「だらりの帯」を締める。およそ6メートルの帯を締めるには、高度な技が要るため、男衆の登場となる(男衆以外が着付けを行う花街もある)。いうなれば、舞妓が住み込む置屋に唯一足を踏み入れることを許された男のプロフェッショナルだ。
だが、男衆の数は年々減り続け、今は5人のみ。そのなかで最年長のベテランが、饗(あい)場幸次(67)だ。お座敷直前の慌ただしい中で、素早く着付けを行う“流儀”をこう語る。
「簡単にするということや、簡単に。複雑に考えたらあかんのですわ。早く着せな、着ている人が呼吸するだけでも着崩れてくるわけです。だから、勢いで着せんと、締まった状態で着せられへん。一気に締めてしまわないとダメなんですわ。」
時間をかけ、丁寧に着せることもできる。しかし、複雑に考えず最短で着付けを終えるには、どうしたらいいか。もうすぐキャリア40年になる饗場がたどり着いた境地だ。
 舞妓・とし恵美さんの着付けをする饗場さん
舞妓・とし恵美さんの着付けをする饗場さん
舞妓といえば、後ろにだらりと垂れ下がった帯。舞妓を小柄に見せ、“おぼこさ”を引き立てる重要な役割を担う。長さ6メートルにもなる“だらりの帯”を手がけるのは、帯職人・三木五鈴(76)。「西陣に、その人あり」とうたわれる名人だ。
三木の自宅兼作業場には、明治時代から伝わる全長約4メートルの手織り機(手機)が3台並ぶ。三木が得意とするのは、のりでぬらした横糸(ぬき)を編み込む『ぬれぬき織り』という技法だ。のりでコーティングされた糸が乾くことで、えもいわれぬ光沢感とハリが生まれる。しかし、織り上がる前に糸が乾くと風合いを損なってしまうため、ひとたび織り始めると途中で休むことは許されず、夏場でさえもクーラーや扇風機をつけない。まさに、時間との競争。西陣で作られる帯のなかでも特に手間がかかる技法といわれる由縁だ。
三木は、したたる汗を拭うこともせず、一定の力で、一定のリズムで、ひたすらに織り続ける。作業中、糸が切れれば、全長4メートルの手機に自らよじ登り、その手で直す。よわい70を越えた三木には、この上り下りはかなりこたえる。落ちて、2回骨折したという。
もはや使い手がほとんどいなくなった伝統の技へと、三木を突き動かすのは、舞妓に対する強い思いだという。
「舞妓さんは着物を着て、帯もええの締めてはったら、『うわ、ええな』と思うしね。しょうもないもん着せられへん。手間をかけるだけ、間違いのないようにせな。」
 手機(てばた)に向き合い、帯を織る三木さん
手機(てばた)に向き合い、帯を織る三木さん
舞妓がまとう、きらびやかな京友禅の着物。友禅師・佐伯昭彦(35)は、舞妓用の着物を年間40着以上手がける注目の職人だ。京都にはあまたの友禅師がいるが、佐伯はただの友禅師ではない。一般に、舞妓の着物は専門の職人によって工程ごとに分業制で作られる。ところが佐伯は、デザインを決める「図案」から、色付けをする「友禅」、さらには金色を施す「金彩」に至るまで、実に10以上の工程を一人でこなすのだ。一人で多くの工程を担うことで、発注主からの要望に瞬時に応えることを可能とし、多くの信頼を得てきた。
しかし、そんな佐伯だが、幼いころは何をやってもうまくいかない少年だったという。勉強もスポーツも、いつもビリ。美術の成績も“1”。高校卒業後、友禅師の父のもとで働き始めたが、からきしダメだったという。そんなとき、舞妓の着物を手がける呉服店のあるじと運命的な出会いを果たす。佐伯は、頭を下げ、舞妓の着物を作らせてもらえるよう懇願した。しかし、舞妓の着物は、一般的な京友禅の着物と配色が異なり、全くうまくいかなかった。
そんな佐伯に、手を差し伸べてくれた人たちがいた。京友禅に関わる職人たちだ。不況で着物が売れなくなり、廃業が相次ぐなか、職人たちは、“伝統を継ぐもの”として佐伯に希望を託し、惜しみなく技術を教えてくれた。そして、「がんばりや」と声をかけてくれたのだった。
それが、佐伯の励みとなった。期待に応えるように研さんを重ね、メキメキと実力を上げた。佐伯は、職人たちから授かった技術や思いを胸に、今、仕事に臨む。
「こうやって絵を描くなりわいができるというのは、僕にとっては“伝統”のおかげだと思っています。こういう巡り合わせで仕事をさせてもらっているので、その道をずっと行きたい。」
 京友禅の技を引き継ぐ佐伯さん
京友禅の技を引き継ぐ佐伯さん
舞妓を支えるのは、目に見えるものだけではない。
匂いで舞妓を引き立てるプロフェッショナルもいる。舞妓が客に配る名刺からほのかに漂ういい香り。その香りをつける“匂い袋”を作る調合師・畑利和(67)だ。
畑は、京都最大手のお香製造老舗の常務でありながら、創業300年の伝統を受け継ぐ調合師だ。だが、単に伝統にしがみつくのではなく、常に新しい発想を取り入れることで斬新なヒット商品を生み出してきた。例えば、舞妓や中高生など若い女性に向けた匂い袋には、これまであまり用いてこなかったエッセンシャルオイルを混ぜ合わせた。
畑は、先代の調合師だった父から秘伝の調合表(レシピ)を受け継いでいる。どの原料とどの原料を合わせれば、どんな香りが生まれるか、その全てが記されている。それでも畑は伝統にとらわれず、日々、試行錯誤を重ね、これまでにない香りを生み出そうともがき続ける。そのぶん、失敗も多いというが、畑を、確固たる流儀が支えている。
「汗を流さないとダメやと、私は思いますね。やっぱり培ってきたものって失わないですからね。お金とかモノとか、どんどん朽ち果てていったりなくなってきますけど、身につけたものは取られないですからね。職人っていうのは当たり前なんですよ、孤独っていうのが。でも、その中で自分っていうものを失わないように、絶えず。」
 原料ボトルを見ながら悩む畑さん
原料ボトルを見ながら悩む畑さん
舞妓は、美しい。
だが、きらびやかに装っているからこそ、舞妓なのではない。
真に求められるのは、その「心」だ。舞妓にとっての“舞台”であるお座敷で、いかに、客をもてなすことができるか。細やかな気配りができる、美しい心を教えるのは、舞妓が住み込む置屋の女将(おかみ)。15歳前後の少女を親から預かり、もう一人の親として彼女たちの成長を見守るプロフェッショナルだ。
舞妓になるには、お座敷の手伝いや踊りの稽古など、およそ10か月の「仕込み」と呼ばれる修行を積まなければならない。女将の駒井文恵(73)は、日常生活から舞妓としての心構えを日々、教える。
半世紀にわたって数々の舞妓を育て上げてきた駒井が説くのは、きれいにお化粧して着飾るだけでは、“ほんまもん”の舞妓にはなれないということだ。
「いい舞妓さんよりも、いい人間にならなあかんえって言います。心がきれいであれば、顔もきれいになるよって。内面を磨いていくことが、一番大切なことやと思うんです。」
舞妓になるということは、京都の花街文化の継承者として生きること。そのためには、内面の心を磨いて成長することが必要だと説く女将の言葉は重い。
 言葉に、人生を預かる重みをにじませる駒井さん
言葉に、人生を預かる重みをにじませる駒井さん