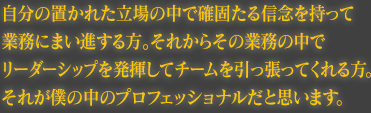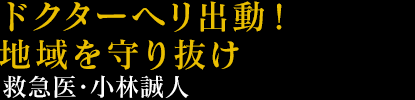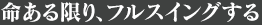ドラマなどで広く知れ渡るようになったドクターヘリ。いま、救急医療の現場で欠かせない存在となっている。そのドクターヘリの出動回数全国一を誇るのが、8年前に開設した、兵庫県豊岡市にある但馬救命救急センターだ。そして立ち上げからセンターのトップを務めてきたのが救急医・小林誠人(48歳)だ。救急医として20年のキャリアを持つ小林は、外科・内科を問わない、幅広い知識と経験を有するスゴ腕。2005年に起った福知山線脱線事故では医療スタッフをまとめ上げる指揮官として活躍した。
その小林、救急医療のあるべき姿を、こう考えている。
「救急医療っていうのは、地域の町の安心安全を担保させてもらう一つの窓口だということです。やっぱり医者というのはそこが原点なんじゃないですか。目の前の患者さんとか自分の患者さんをちゃんと診てという。その結果として、地域の町作りの一つの歯車として回っていけばいいんじゃないですか。」
救急医療は、地域を支える“歯車”であるべき―。小林は、その強い思いを胸に、日々現場へと向かっている。
![]()

![]()
 小林たちのドクターヘリが管轄するのは、病院を拠点に半径80キロ圏内。東京をはるかに凌ぐ広域だ。
小林たちのドクターヘリが管轄するのは、病院を拠点に半径80キロ圏内。東京をはるかに凌ぐ広域だ。
脳卒中や心筋梗塞、交通事故など小林のもとには、命の危機にひんした患者が日々運び込まれてくる。ときには、どれだけ力を尽くしても救えない命があるのが現実だ。
しかしそれでも、小林は1%の助かる可能性に懸けて、力を出しきる。
「人間は確かに、必ず亡くなるんだけども、その人に与えられた残りの人生が何年かあって、それを全うさせるために、ここのけがを治さないといけない、治してあげることができるっていうんであればやっぱりフルスイングするべきだし。フルスイングして助かる可能性3%が、100%になることだってあるんです。とことんやって、とことんやり尽くして、考え尽くして、そこで出てきた結果を見つめないと。」
たとえ医師でも、『命の限界』など決められないという小林。常にフルスイングして患者と向きあってきた結果、但馬地域の救命率は格段に上がった。
 キャンセルもいとわずドクターヘリで駆けつける小林たち。出動回数は年間1,900回以上。地域のためにドクターヘリをどう活用できるか、更なる高みを目指している。
キャンセルもいとわずドクターヘリで駆けつける小林たち。出動回数は年間1,900回以上。地域のためにドクターヘリをどう活用できるか、更なる高みを目指している。
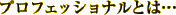 画像をクリックすると動画を見ることができます。
画像をクリックすると動画を見ることができます。