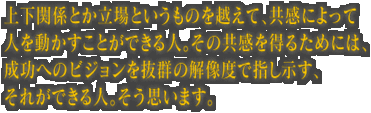“飽和市場”と言われて久しいお菓子市場。チョコレート菓子だけでも年間1,000個以上の新商品が出るが、1年後まで店頭に残るものはほとんどない。日々熾烈(しれつ)な競争が繰り広げられる業界で、客の心をつかみヒット商品を連発するのが、大手菓子メーカーのチョコレートマーケティング部部長の小林正典(44)だ。緻密な市場分析を重ね隠れたニーズを発掘し、アイデアを突き詰めていくことで、新ジャンルの商品を次々と生み出してきた。横ばいだった看板商品の売り上げもこの5年で50億円伸ばしてきたヒットメーカーだ。だが、ヒットへの道は決して平坦なものではない。巨額の投資をしたものでも、結果が出なければすぐに市場からの撤退を余儀なくされる世界。開発には、常に失敗と挫折がつきまとう。くじけそうになる時でも、小林はひとつの信念を胸に、挑み続けている。
「怖いですよ。長いものなら3年ぐらい考えてきて、(販売して)1週間で結論が出ますからね。やったこともないことを、だいたい難しいと言っているので。それを短縮すると、『難しいは、新しい』になると。できることだけやっても絶対サプライズはできないですよ。失敗を失敗で終わらせたら、失敗っていうだけで。次どうする?って考えているうちは失敗じゃないと思っているので」
![]()
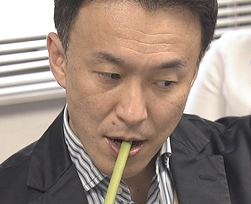
![]()
 新しいからこそ、難しい。
新しいからこそ、難しい。
部下に開発者の矜持(きょうじ)を伝える。
消費者がスーパーやデパートで商品を選ぶ時間は、わずか2秒だと言われる。その一瞬で客の心をつかむために小林がこだわるのが、商品の“ストーリー作り”だ。客がどんな場面でどんなお菓子を食べたいと思うか具体的な場面を想定し、それに合う味やパッケージ、キャッチコピーなど細部を突き詰めていく。例えば主婦をターゲットにしたチョコレートの場合は、こんなストーリーを描く。「子どもを送り出したあとも家事で忙しい。15分のコーヒーブレイクしか取れないけど、とっておきの休憩にしたい。そんな時に、次の家事も頑張ろう!と思える一口で満足できる濃厚なチョコレート」。ここまで徹底的に商品のコンセプトを詰めると、消費者は「あ、まさにそれが欲しかった!」とついつい手を伸ばしてしまうという。
「私のあの時のあのシーンで、このお菓子ピッタリかも!と2、3秒間で思わせる、思って頂けることが大事で。何らかのシーンに合うなって思わないと絶対お客さまに手を出して頂けないですよ。お客さまの共感を得ないと、買い物カゴの中に入りませんので。伝わらなければ負けだし、伝われば勝ちだしということ」
 客の心を2秒でつかむヒントを日々探す。
客の心を2秒でつかむヒントを日々探す。
15人の部下と120種類の商品を日々リニューアルしながら新商品を開発する小林。その主戦場は、会議室だ。1日の仕事の9割は会議で、自席にいる時間はわずか1時間程度。多忙を極める中でも、小林は会議に最も時間をかける。その方法は独特だ。部下からの報告を聞いた後、「なぜ?」「なぜ?」と質問攻めにする。商品の魅力を2秒で伝わるウリとなるまで、徹底的に詰めていくためだ。その部下を問い詰める姿は、時に禅問答のようだ。小林自身も、何が正解かは分からない。だからこそ、部下の直感を信じ、客の心に響く“何か”にたどりつくまで、ともに徹底的に議論を深めていく。
「ミーティングや打ち合わせの時間をもっと省いて、直線的に物事を進めていくというやり方もあるかもしれないですけど、その先には小さな成功しかないような気がしていて。大きな成功を生み出すには、大きく蛇行しながら、混沌としながら、議論を重ねながら、全身からすべてを出し尽くした先に「お!それいいね!」っていう瞬間が一瞬下りてくると。そこまで議論する」
 正解はない。部下の直感を信じ、議論を繰り返す。
正解はない。部下の直感を信じ、議論を繰り返す。
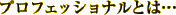 画像をクリックすると動画を見ることができます。
画像をクリックすると動画を見ることができます。
入社当初から10年間、営業一筋だった小林。成果が上がらないと「マーケはもっといい商品を作ってくれなきゃ困る」と不満を募らせていた。そんなある日、マーケティング部に異動となるが、いざ自分でやってみると、全くアイデアが出せず、当惑する。上司や仲間に手伝ってもらい、なんとかヒット商品を作ったが、「自分は何ができたのか。ビギナーズラックではないか」と思い悩む。そんな時に、社内で「失敗作」と言われていたチーズ棒に出会う。その作者である研究所の細川誠司もまた、ヒット作のない男だった。「一発当てたい」と2人で試行錯誤を始めた。アイデアを出し合い、互いに張り合い、相手の要望以上のものをやり遂げる中で改良を重ねていった。次第に2人の熱意は、営業や広告、物流部門へと伝わり、仲間の輪が広がっていった。こうして「一緒にやろう」という共感が渦のように広がることで、年間50億円を売り上げる大ヒット商品が生まれた。
 社内では「失敗作」と言われたチーズ棒
社内では「失敗作」と言われたチーズ棒
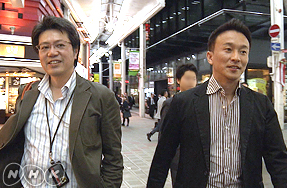 今も良きライバルであり、パートナーである細川
今も良きライバルであり、パートナーである細川