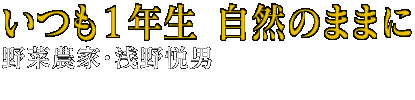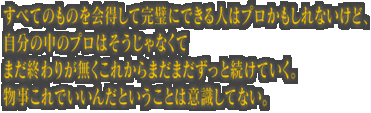浅野の野菜は、その味の確かさから、国内外の多くのシェフから愛されている。
“厨房のピカソ”の異名をとる三ツ星フレンチシェフ、ピエール・ガニェール氏も心酔するひとりだ。
極上の味が生まれる秘密、それは浅野が50年地道に続けてきた畑作りにある。
浅野は化学肥料や有機肥料を最低限しか用いず、畑を徹底的にやせさせる。そして日本の土壌では不足しがちなミネラル分を、かき殻で補うことで、野菜本来の味を引き出していく。さらに、野菜を植える前に畑に麦わらを混ぜ込む作業を、丹念に何度も繰り返して土中の微生物を増やし、土を柔らかくする。すると野菜自身が根を遠く深く伸ばすことができ、自らの力で養分を探し出して取り込む力が引き出され、しっかりとした味の野菜に育つという。
野菜を大きく太らせたり収量を上げたりすることを目標とせず、野菜自らの「生きようとする力」を引き出すことに特化する。それが、浅野が半世紀にわたって続けてきた地道な野菜作りの本質だ。
![]()

![]()
 命の息吹が香り立つ野菜
命の息吹が香り立つ野菜
 野菜の生きようとする力を引き出す
野菜の生きようとする力を引き出す
浅野は、畑の中にあるビニールハウスで、世界各地のめずらしい野菜を実験的に育てている。
中には、種をまいてもまったく芽を出さないものもある。芽が出ても、まともな野菜に育て上げるまでに3年以上かかることもしばしばだという。そんな困難に直面するとき、浅野はけっして焦らない。未知の植物である以上、だめだと思った種から急に芽が出ることもあれば、その逆もある。ひたすらに自然を見つめ、命を学び取る。そうして自らを常に戒める。「50年たっても、ずっと1年生」だと。
5月、浅野はある新しい野菜の栽培に挑んでいた。シーアスパラガスという、海岸付近の塩分を含んだ土で育つ特殊な植物だ。これまで5年挑むもことごとく失敗に終わってきた。今年こそと背水の陣で挑む浅野。こだわるのにはひとつの大切な理由があった。2年前に起きた東日本大震災で、津波の塩害のため今なお作物を育てられない農家もいることに、浅野は心を痛めていた。このシーアスパラガスなら海水につかった農地でも育てられるのではないかと、希望を抱いていたのだ。浅野は、今後誰もがこの野菜を育てられるようにと、自らの畑をあえて海岸に近い状態にして栽培方法を模索するのだった。
 シーアスパラガス
シーアスパラガス
 悲願の野菜に希望をつなぐ
悲願の野菜に希望をつなぐ
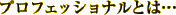 画像をクリックすると動画を見ることができます。
画像をクリックすると動画を見ることができます。
浅野は、育てた野菜をただシェフに届けるだけでは満足しない。まず、火を入れるとどう味が変化するのかを自ら把握し、シェフがどう使いたいのかという細かな要望にも耳を傾ける。最終的に、その野菜を使った料理を客に楽しんでもらうということが、浅野にとっては重要なのだ。
そんな浅野がフェイスブックを使いこなし取れたての野菜の写真をシェフたちに発信する姿は、まるで自分の子どもを自慢する親のようだ。
 火を入れて味がどう変わるか?
火を入れて味がどう変わるか?
 育てた野菜は自分の子ども
育てた野菜は自分の子ども
浅野は、市場では扱われない部分や規定サイズに満たない物など、いわゆる「規格外」として市場では値がつかないような野菜をも、積極的に商品にしている。例え規格に満たなくても、そこには植物本来の価値が必ず備わっていると考えるからだ。浅野は、その価値に生産者側が気づくことが大切だと考える。「自然の前では、ずっと1年生」と自らを戒める浅野ならではの発想だ。
たとえば大根。通常は捨てられてしまう花や種ざやなどは、食べると大根独特の甘みや辛みがある。浅野はそれを商品化し、レストランの料理にと提案していく。
 大根の種ざや・花・つぼみで皿を彩る提案
大根の種ざや・花・つぼみで皿を彩る提案