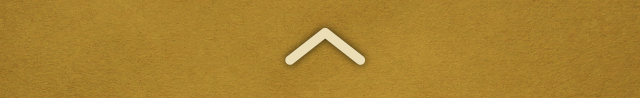若松英輔
(わかまつ・えいすけ)
批評家
1968年、新潟県生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒業。2007年「越知保夫とその時代─―求道の文学」にて第 14 回三田文学新人賞評論部門当選。2016年『叡知の詩学─―小林秀雄と井筒俊彦』(慶應義塾大学出版会)で第2回西脇順三郎学術賞を受賞。著書に『神秘の夜の旅』(トランスビュー)、『魂にふれる─―大震災と、生きている死者』(トランスビュー)、『霊性の哲学』(KADOKAWA/角川学芸出版)、『生きる哲学』(文春新書)、『悲しみの秘義』(ナナロク社)、『イエス伝』(中央公論新社)など、和合亮一との共著に『往復書簡─悲しみが言葉をつむぐとき』(岩波書店)。
◯『苦海浄土』 ゲスト講師 若松英輔
『苦海浄土』とは何か
『苦海浄土』は、一九六九年に刊行され、翌七〇年の第一回大宅壮一ノンフィクション賞に選ばれます。しかし、著者の石牟礼道子は受賞を辞退しました。
理由は、公表されていませんが、彼女の自伝を読むと、大きく二つあるのではないかと考えられます。一つは、この作品がいわゆる「ノンフィクション」ではないこと、そしてもうひとつは、自分はこの作品の真の作者ではない、と彼女が感じていたところにあるように思われます。
近代文学では通常、作者がいて作品がある、作品は作者に属するものである、と考えられます。社会的にはもちろんその通りなのですが、『苦海浄土』をめぐっては、本質的にはそれとは異なる意味があります。少なくとも石牟礼にはそう感じられていたように思われます。『苦海浄土』は水俣病の患者たちが本当の語り手であって、自分はその言葉を預かっただけなのだ、という強い自覚が彼女にはある。表現を変えながら彼女は様々なところで、水俣病の患者たちは、言葉を奪われて書くことができない、自分はその秘められた言葉の通路になっただけだと語っています。
ノンフィクションでなければフィクションなのか、ということになりがちですが、私たちは、そもそも文学を、ノンフィクション、フィクションで二分しなくてはならないのでしょうか。
作家の遠藤周作が新約聖書にふれ、この書物は、文学としても、もっとも優れた作品であるといい、そこには事実だけではなく、その奥に秘められた真実も描かれていることを読者は忘れてはならないと語っていましたが、同じことは『苦海浄土』にもいえると思います。
本文でもふれますが、この作品の成り立ちをめぐって彼女と話をしたことがあります。そのとき、彼女は、現代詩の枠組みを超えた新しい「詩」のつもりで書いた、と語っていました。
『苦海浄土』は、詩である、と聞くと何か違和感を覚えるかもしれません。ただ、ここでいう「詩」とは、単に文学の一形式としての「詩作品」であるだけでなく、文学の根源的な精神を表象する「詩情」の結晶である、と考えることができるのではないでしょうか。また、詩には決まった形式は存在しないということも、ここでもう一度思い出したいと思います。
ともあれ、『苦海浄土』という作品が、既存のどのジャンルにも当てはまらない、まったく新しい文学の姿と可能性を伴って現れた、二十世紀日本文学を代表する作品であり続けていることは、すでに動かせない事実となっています。
『苦海浄土』の第一部は、全七章からなる作品ですが、第一章から順に書かれたのではありません。第三章の「ゆき女きき書」に当たる部分から誕生しました。それを核にして、あたかも何者かによって光が放たれるように作品世界が広がっていきます。
現在、第三部までは公刊されていますが、第一部に続いたのは第三部『天の魚』(一九七四年)でした。そして第二部『神々の村』(二〇〇四年)が書かれたのです。今もその営みは続いています。今回はそのなかでも特に第一部に軸足をおいてこの作品を読んでみたいと思います。この第一部は作家石牟礼道子の原点であり、それを読むことはおそらく現代日本文学の大きな岐路を目撃することになるからです。
時間は過去から未来へと進んでいく、私たちはそう信じて疑いません。しかし、この作品には、過ぎ行く時間とは別の永遠につながる「時」が描かれています。ある文章で石牟礼は、水俣病で亡くなった人は「未来へゆくあてもないままに、おそらく前世にむけて戻ろうとするのではあるまいか」(『わが死民――水俣病闘争』)とすら述べています。
計測可能な時間のなかで、すべてのことは過ぎ去ってしまうのか。けっして過ぎ去ることのない永遠に連なることが、この世にはあるのではないか。生命は滅びる。しかし、万物の「いのち」はけっして朽ちることがないのではないか、と彼女は全編を通じて読者に問いかけてきます。
『苦海浄土』を書いているとき、どんな心境でしたかと彼女に尋ねたことがあります。しばらく沈黙してから彼女は「荘厳されているように感じました」と答えました。
「荘厳」とは、もともとは仏教の言葉で、仏の光によって深く照らしだされることを意味します。また、荘厳という言葉には人間の感覚を超えた響き、香り、輝きが広がり、また何ものかに包み込まれるような語感があります。真の意味における浄福と考えてもよいかもしれません。しかし、石牟礼が用いる場合には、特定の宗教的背景はありません。彼女が書くと、その底には留まらない広がりと深まり、さらには深い悲しみがあることに気づかされます。
荘厳の光は、苛烈な、ときに残酷なまでの苦しみを生き抜いた水俣病の患者とその家族の言葉にならない祈りによってもたらされている、それが石牟礼道子の今も続く強い実感です。『苦海浄土』を読む意味は、石牟礼を通じて、苦難を生きたものから発せられる「荘厳」の働きにふれることである、ともいえると思います。
『苦海浄土』は、単なる告発の文学ではありません。むしろ、光源の文学です。水俣病の原因を作った企業あるいは地方行政、国家行政の欠落を照らし出すだけでなく、言葉を奪われた人々の心の奥にあるものも、白日のもとに導き出すのです。
もしかしたら皆さんのなかには、『苦海浄土』を読もうと思ったけれど、誤った理解をしてしまうのが怖くて、あるいは悲劇にふれるのが恐ろしくて、これまで手に取らなかったという方もいるかもしれません。私にもそういう時期が長くありました。
しかし、そもそも「正しい」読書方法などあるのでしょうか。文字の正しい読み方はあります。しかし、本の正しい感じ方などありません。百人の読者がいれば百通りの『苦海浄土』があってよい。異なる読後感であっても、それが真摯に語り合われるとき、そこには豊かな響き合いが生まれます。ただ、自分の読みが絶対だと思わないことは重要です。
文学がもし、言葉の芸術であるなら、それにふれる者は何を感じてもよいはずです。絵画を見るとき、音楽を聴くとき、彫刻にふれるとき、私たちはとても自由にそれらを認識しています。そして他者の認識をとがめない。どうして文学を読むときにはそれができなくなってしまったのでしょう。自分の認識をいつくしむことができず、自分と異なる感覚を認めづらくなったのでしょうか。
また、私たちは必ずしもこの作品を読み通す必要はありません。「読めない」のは、そこで立ち止まらなくてはならないからです。読書は旅です。むしろ、読み通すことのできない本に出会うことこそ、喜びなのではないかと私は思います。「読めない」というのはじつに深遠な言葉との交わりであり、また豊饒な芸術の、あるいは人生の経験であることを忘れないでいただきたいと思います。
さらに、先ほどもふれましたが、この作品の語り手は石牟礼道子だけである、というところから読者である私たちは、一歩、踏み出すことが求められているように思います。彼女の果たしている役割が、甚大であり、深甚なのは改めていうまでもありません。彼女こそ、現代日本が世界に、そして歴史に対して誇るべき屈指の書き手であるとも思います。そうした事実を踏まえてなお、彼女の言葉として読むのではなく、彼女に託された言葉として読む。本当の苦痛、苦難を抱えている人は、彼女の後ろにいるのだということを、私たちは見続けなければいけない。それが読者の役割であり、作者である石牟礼の悲願であるように思われるのです。
本当の芸術は、最後には人の心を慰め、励まし、そして、真実の美によって包み込みます。『苦海浄土』はそうした典型的な、しかし、現代日本ではじつに稀有な作品なのです。
このテキストと番組が、そうしたみなさんと『苦海浄土』の出会いの一助となれば望外の幸いです。