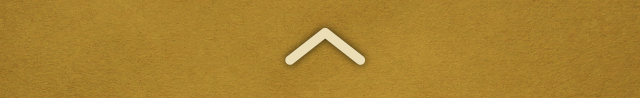上野千鶴子
(うえの・ちづこ)
社会学者、東京大学名誉教授
1948年、富山県生まれ。認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク(WAN)理事長。専門学校、短大、大学、大学院、社会人教育などの高等教育機関で、40年間教育と研究に従事。主な著書に『近代家族の成立と終焉』『家父長制と資本制』(ともに岩波現代文庫)、『おひとりさまの老後』(文春文庫)、『おひとりさまの最期』『女ぎらい』(ともに朝日文庫)、『ケアの社会学』(太田出版)など多数。近著の『在宅ひとり死のススメ』(文春新書)では、慣れ親しんだ自宅で幸せな最期を迎える方法を提案している。
◯『老い』 ゲスト講師 上野千鶴子
老いてなにが悪い!
シモーヌ・ド・ボーヴォワール(一九〇八~八六)は、ジャン=ポール・サルトルと並び、戦後フランスにおいて実存主義の思想を掲げて活動した作家・哲学者です。代表作『第二の性』(一九四九年)は、一九六〇年代のウーマン・リブ以降のいわゆる第二波フェミニズム(第一波は十九世紀末からの婦人参政権運動)の先駆けとなった著作で、世界の女性たちに大きな影響を与えました。「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」という有名な一節は、現在のジェンダー研究の最先端、すなわち、性差は運命でも単に生物学的なものでもなく、社会的に構築されるものである、という視点を先取りしていました。
ボーヴォワールの著作でわたしが最初に読んだのは、やはり『第二の性』でしたが、今回はボーヴォワールが『第二の性』の約二十年後、六十二歳で発表した『老い』(一九七〇年)を取り上げることにしました。なぜかって? それはわたしが老いたからです。現在のわたしにとって、自分と同じような年齢の人たちがその時々でどういうことを考えたかは大きな関心事です。老境に入ったボーヴォワールが、老いについてどう考えたのかにも非常に興味があります。
しかしながら、この本に対するわたしの関心は、自分が年をとって初めて芽生えたものではありません。以前から、いつかこの本にきちんと向き合いたいと考えていました。というのも、老いを初めて自覚した三十代の頃に初めて読んだとき、「老いは文明のスキャンダルである」というボーヴォワールの言葉に大きな衝撃を受けたからです。ボーヴォワールがこの本を書いた動機は、現代社会において老人は人間として扱われていない、老人の人間性が毀損されている、ということへの怒りでした。『老い』の序文では、変化の速い消費社会において老人は「廃品」として扱われていると言い、こう述べています。
人間がその最後の一五年ないし二〇年のあいだ、もはや一個の廃品でしかないという事実は、われわれの文明の挫折をはっきりと示している。(中略)この人間を毀損する体制[システム]、これがわれわれの体制にほかならないのだが、それを告発する者は、この言語道断な事実[スキャンダル]を白日の下に示すべきであろう。(朝吹三吉訳、人文書院)
文明社会でありながら、老いた人間を厄介者にして廃物扱いする。そのように老人を扱うことが文明のスキャンダルであると、ボーヴォワールはきっぱりと言っているのです。当時、ここまではっきり述べた人は他にいなかったでしょう。以来、「老いは文明のスキャンダル」という一行がわたしのなかでずっと鳴り響いてきました。
ボーヴォワールの主張は、つまるところ、老いは個人の問題ではなく社会の問題である、ということです。この主張は、わたしの研究者としての出発点である女性学の視点とも響き合います。
わたしが三十代で出版した『女という快楽』(一九八六年)という本には、「おんな並みでどこが悪い」という論考があります。当時は、女が地位を向上させたかったらまずは女自身が意識を変えてがんばりなさい、と言われていた時代です。それに対し、ただの男が普通に家庭も子どもも仕事も持っているのだから、ただの女だって男並みに努力せずともそれらを持てて当たり前じゃないか、女に対し「がんばって」とは口がさけても言いたくない、女の解放に不可欠なのは女の努力ではなく社会の変化だ、と書いたのです。「同じにならなければ排除される社会」ではなく、「違っていても差別を受けない社会」――八〇年代にこれを書いたのはかなり早かったでしょう。
違っていても差別されない社会を考えていくなかで、これは女性のみならず、広く「社会的弱者」と言われる人びとに共通する問題だと気づきました。そこから高齢者や介護問題を研究するようになり、現在に至ります。
さて、わたしは今も「老いても若々しくいましょう」とか「老いても前向きに生きましょう」などとは口がさけても言いたくありません。なぜなら、老いとは誰もが抗えない衰えの過程だからです。老いは誰にも避けられません。なのに、なぜその過程を否定しなければならないのでしょうか。ボーヴォワールは『老い』のなかで、厄介者になった高齢者をどう扱うかで、その社会の質が測られると言っています。老いとは個人が努力で克服するものではなく、まさに社会の問題であり、文明の問題なのです。
変革のためには、まず現実を知ることが必要です。ボーヴォワールは膨大な資料を読み解いて、厄介者扱いされる高齢者の現実を直視します。また「自分は厄介者になってしまった」と悲嘆する高齢者の心理をも直視します。そして、老いとはこんなにもみじめでみっともないものであるということを、これでもか、これでもかと書いています。読んでみるとわかりますが、『老い』は陰惨な本です。前向きに老いるヒントなどほとんど書いてありません。しかし同時に、全世界で高齢化率が上がり、高齢あるいは超高齢社会に突入した現在の老いの問題を先取りした、先駆的な本でもあります。
『老い』は『第二の性』と並んで、ボーヴォワールの主著の一つとみなされるまでになりました。今回は、老いを自己否認するしくみ、さまざまな社会や職業別の老い、老いと性、老いの社会保障という四つの視点から、みなさんとともに読んでいきたいと思います。