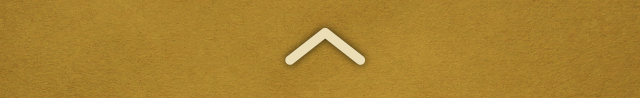戸田山和久
(とだやま・かずひさ)
名古屋大学大学院 情報学研究科教授
1958年東京都生まれ。東京大学大学院人文科学研究科単位取得退学。専攻は科学哲学。著書に『思考の教室』(NHK 出版)、『新版論文の教室』『科学哲学の冒険』(以上、NHK ブックス)、『「科学的思考」のレッスン』『恐怖の哲学』(以上、NHK出版新書)、『論理学をつくる』『科学的実在論を擁護する』( 以上、名古屋大学出版会)、『知識の哲学』(産業図書)、『哲学入門』(ちくま新書)、『教養の書』(筑摩書房)など。
◯『華氏451度』 ゲスト講師 戸田山和久
寓話としての『華氏451度』
本を読むこと、本を所有することが禁じられた近未来世界。本を持っていることが当局に知られると、「ファイアマン」が駆けつけ、本を家ごと焼却してしまう。そんな世界で誇りをもって忠実に職務に励む一人のファイアマン、モンターグが、本を燃やす仕事とそれを必要とする社会のあり方に疑問を抱くようになり、しまいには社会を捨て、本を守り伝える人間として生きていくことを決意する。
アメリカのSF/ファンタジー作家レイ・ブラッドベリ(一九二〇~二〇一二)が一九五三年に発表した長編小説『華氏451度』は、主人公モンターグの成長と回心の物語であり、彼が「啓蒙」されるプロセスを描いた小説です。文学の伝統においては、こうした小説は教養小説(ビルドゥングスロマン)と呼ばれてきました。
今回とりあげるにあたって、いろいろ評論を読んでみました。すると、本作品はブラッドベリの代表作とされているわりには、作家や文学研究者など「その道のプロ」には必ずしも評判がよくないということに気づきました。曰く、安っぽい感受性(キングズレー・エイミス)、時代遅れ(ハロルド・ブルーム)、などなど。けっこうな言われようですね。たしかにそうした面があることは否めません。でも、この小説はシリアスなSFというより、むしろ寓話だと考えてみたらどうでしょう。寓話はたとえ話ですから、そもそもペラペラしていて図式的なところがあるのは当たり前。では、何についての寓話なのか。それは、私とみなさんが生きている現代社会についての、です。
本作のタイトルになっている華氏451度(摂氏233度)は紙が自然発火する温度です。この作品はディストピア小説の典型例とも見なされています。「ディストピア」とは、「ユートピア(理想郷)」の反対語です。「暗黒郷」とでも訳せばいいでしょうか。ディストピアなるものは、現実とはまるきり違う悪夢のような世界、と思われがちですが、じつはそうではありません。ディストピア小説は、私たちが暮らす現実社会の危うい面や暗黒面をちょっとだけ延長して、いまとほとんど変わらないけれど少し極端になった未来を描きます。それによって、私たちが住む社会だって見方を変えればこういうものなのですよ、と教えてくれます。つまり、現実社会の批判こそが、ディストピア小説の最も大切な役割なのだと言えるでしょう。
執筆後半世紀以上を経たいまになって、あらためてこの小説を読むべき理由は二つあるのではないかと思います。
ディストピア小説としての『華氏451度』は、意識して「いまと変わらない未来」を描こうとしています。小説の舞台は二十一世紀中盤とおぼしきアメリカ。執筆当時から見て一〇〇年近くたった未来社会のはずなのに、じつに一九五〇年代っぽいところがあって、登場するテクノロジーもそれほど未来らしくありません。たとえば、自動車の速度は格段に上がっているものの、ハイスピードで運転しても道路脇の看板がちゃんと読めるようにと、看板がものすごく横長になっていたりします。デジタルサイネージ(電子看板)や車々間通信を応用した別のハイテク広告技術が生まれているわけではなく、看板という古くさいテクノロジーがそのまま使われているのですね。ですから、この作品は未来を空想したものというより、むしろ大衆消費社会が本格的に到来した当時のアメリカ社会そのもののパロディと読むこともできます。
ほかにも、この小説にはまさに当時 (そして現在)のことが書かれていると思えるような箇所、それどころかいまの現実の方が先を行っているじゃないかと思えるような箇所がたくさんふくまれていて、しかもそれらがすべてディストピアを構成する重要な要素として描かれる。ここが重要だと思います。いまの「当たり前」は、ちょっと違った角度から見ればそのまんま地獄である、ということになるからです。
このように、われわれの生きる現実を、ひょっとしたらこれは地獄かもしれない、という批判的視点から見る。これが、いま『華氏451度』を読むべき第一の理由です。
第二の理由は、その道のプロの見解に反して、この作品はなかなかどうしてけっこう複雑だということ。冒頭のようにあらすじをまとめてしまうと、たんなるノスタルジックな読書礼賛小説だと思われるかもしれませんが、この小説は「読書が禁じられている社会って怖いですね」「やっぱり本っていいですよね」という単純なものではありません。コミュニケーションの本質、歴史と記録、知識人と大衆、都市と自然、権力のしくみなど、多岐にわたる問題がごちゃ混ぜになって描かれています。しかもすべて未消化で、さまざまな混乱や矛盾もあります。したがって、読者はこれらの問題を自分で引き受けて、自分で考えていかなければいけません。すぐれた小説は、簡単には答えの出ない問いを読者に投げかけ、自分自身で考えることを促してくれるものでしょう。だからこそ読むべきなのです。
『華氏451度』は、フランスの映画監督フランソワ・トリュフォーによって一九六六年に「華氏451」のタイトルで映画化されています。じつは、私がこの作品に出会ったのは小説ではなく、映画版を通してでした。しかも封切りでは観ておらず、中学生の頃テレビで放映されたものを観たのが最初でした。当時は「〇曜洋画劇場」といった番組が毎日のように放送されていて、テレビでたくさんの映画を観ることができたのです(しかもタダで)。私が中学生になる前後の頃は、暗くて苦い近未来ものが流行っていました。「猿の惑星」(六八)、「時計じかけのオレンジ」(七一)、「ソイレント・グリーン」(七三)、少し飛んで「未来世紀ブラジル」(八五)。どれも大好きですが、「華氏451」は特に好きでした。ラストシーンが美しく、切なく、詩的で、その後もレンタルビデオやDVDで、繰り返し観ています。
そんな大好きな映画の原作はどんなものだろうと初めて小説を読んだのがおそらく大学生の頃。映画とはだいぶ違うな、というのが第一印象でした。プロットはほぼ同じなのですが、大事なところがいろいろと違うのです。その違いについても、これから小説を読み解く中でお話ししていきたいと思っています。
ではみなさん、本が燃やされるディストピアへようこそ。