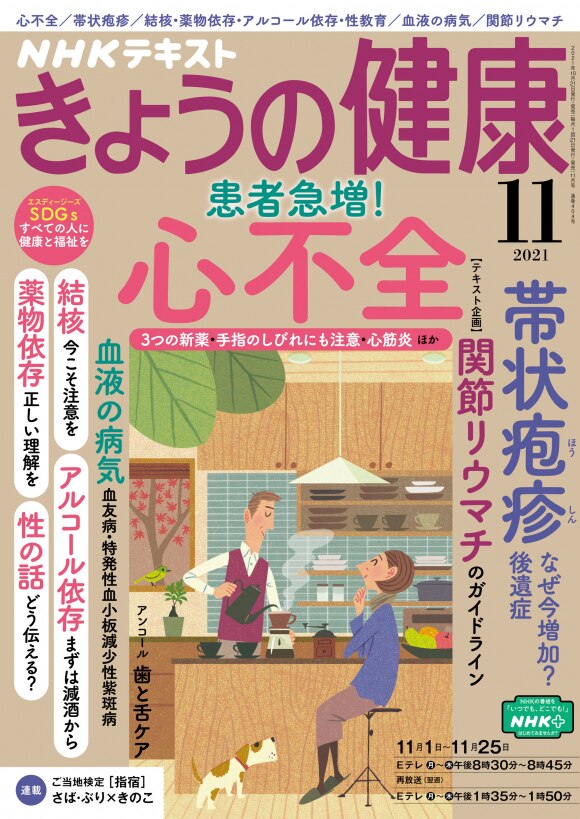“心の弱さ”のためではない
有名人の薬物使用、特に再使用が報じられると、インターネットなどで激しいバッシングが起こります。薬物の使用が“心の弱さ”のため、“自分への甘さ”のためと考えているからだと思います。しかしそれは誤りです。
覚醒剤などの薬物を使っていると脳の状態が変化してしまいます。これまでになかった強烈な欲求が新たに生まれ、自分の行動をコントロールできなくなってしまうのです。意志や資質の問題ではなく「治療が必要な病気」と捉えることが大切です。
“犯罪者”のレッテルは再起を妨げる
薬物を使った人はしばしば“犯罪者”というレッテルを貼られます。周囲から拒絶され、電話をかけても誰からも着信拒否され、仕事も見つかりにくくなります。そうした孤立のつらさから逃れようとして、再び薬物を使ってしまうこともあります。犯罪者としてのバッシングはむしろ再起を妨げるのです。
そもそも薬物依存症は国際的には「再発と寛解を繰り返す慢性疾患」とされています。「3歩進んで2歩下がる」を繰り返しながら少しずつ良くなっていきます。「再発は想定内」ということです。仮にその人が再び薬物を使ったとしても、「やっぱりダメだった」とは思わないでほしいと思います。
「ハームリダクション」による解決を
薬物依存の問題を解決するため、ヨーロッパなどでは厳罰主義から「ハームリダクション」(薬物の害をできるだけ減らす)という方針に変わってきました。国連もこれを推し進めています。
たとえばスイスでは、1970年代に違法薬物ヘロインがまん延したため、法律を改正して厳しく取り締まりましたが、逆に使用者が増えてしまいました。そこで1990年代に治療や支援に重きをおくハームリダクション政策に切り替えました。その結果10年前後のうちに新規のヘロイン使用者は1/6から1/5に、ヘロイン所持の検挙件数は1/3に減少しました。
周囲の人はどう接したら?
自分の地域や職場に薬物依存から復帰しようとしている人がいたら、どうしたらいいでしょう。薬物依存を従来のイメージや先入観で眺めず、本当はどういう病気なのかをまず勉強してほしいと思います。
また、その人が医療機関や自助グループに通っていたら、ぜひ褒めてください。「なんだ、まだ病院に通っているのか、いつになったら治るんだ」と言う人がいますが、治療の妨げになります。薬物はいったんやめるのは簡単でも、やめ続けることこそ難しいのです。したがって、通院していることこそ回復に向かっているあかしだと考えてください。