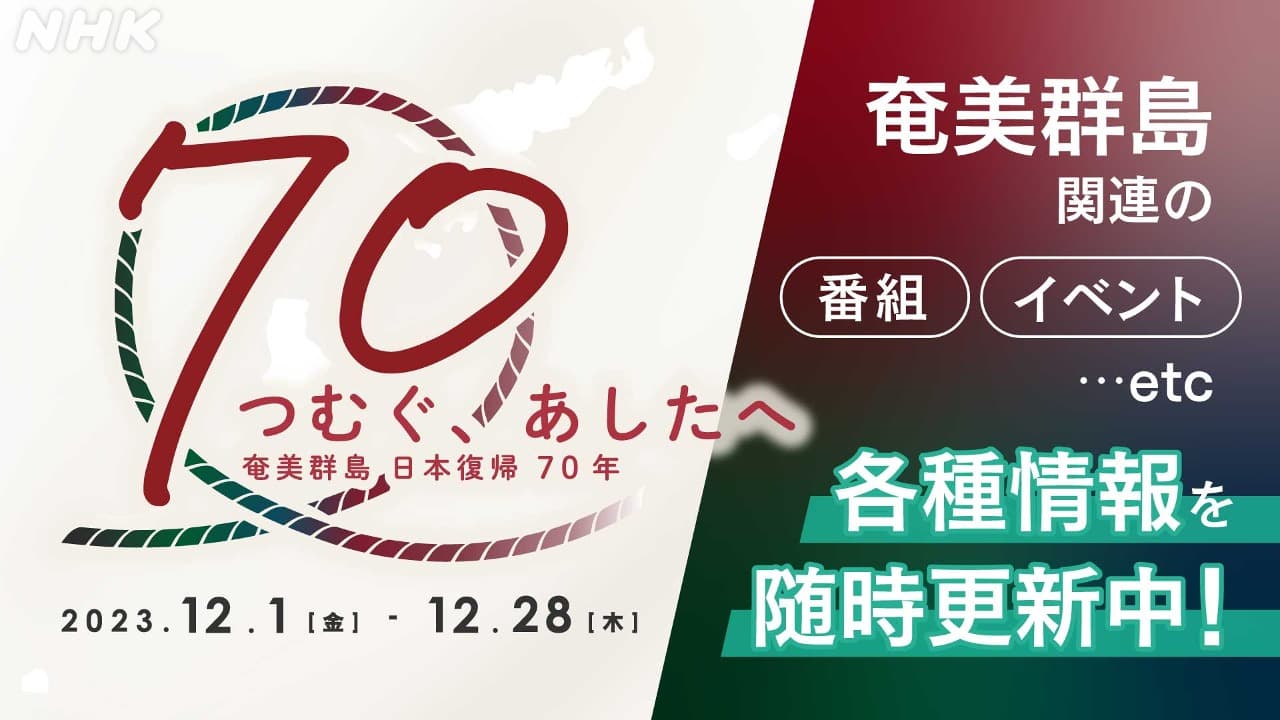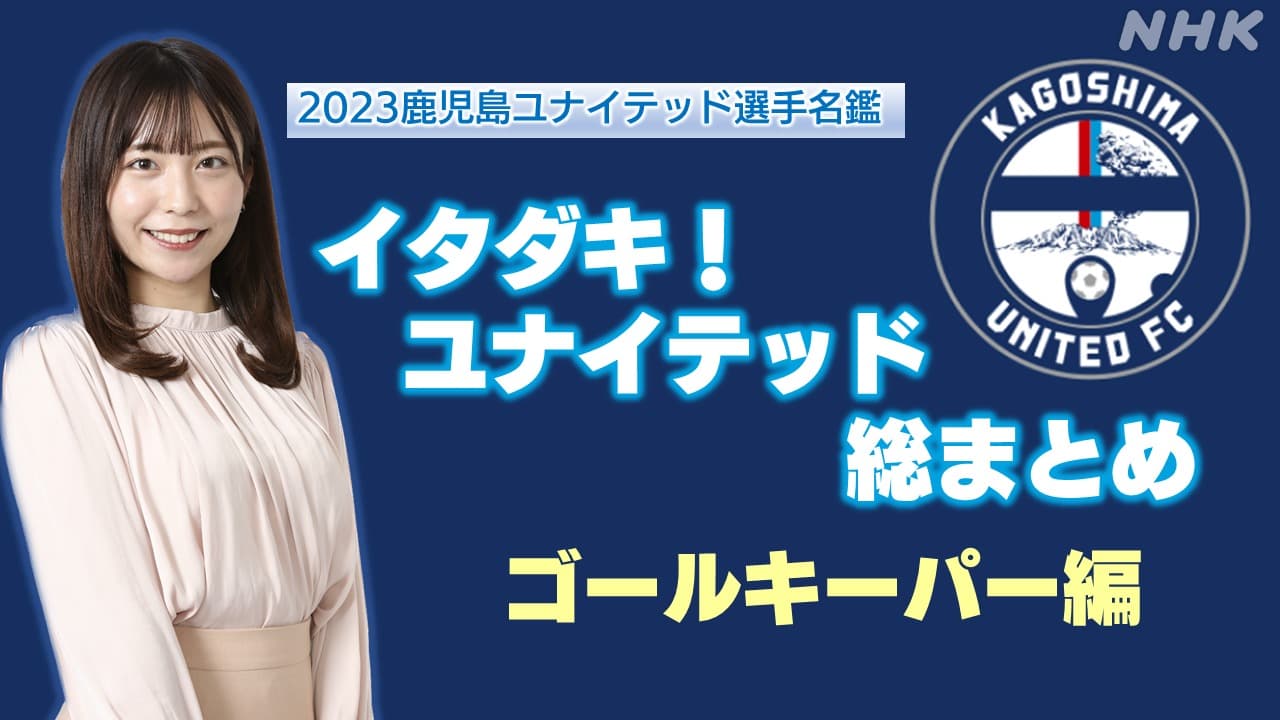奄美復帰70年 復帰運動の記憶をつないで
- 2023年12月15日
奄美群島の日本復帰への大きな原動力となったのが、空前の盛り上がりを見せた復帰運動です。復帰を求める署名活動には、わずか2か月あまりで14歳以上の99.8%が署名。まさに“島ぐるみ”の運動でした。復帰運動が今に伝えるものとは何か。徳之島で運動の中心となって活動した男性を取材しました。
鹿児島局記者 古河美香

思いはひとつ“日本人は日本に帰せ”
徳之島に住む田袋吉三さんは1927年生まれの96歳。
70年前に復帰運動に身を投じたひとりです。昔の写真を見せながら当時を振り返りました。

田袋𠮷三さん
この写真はちょうど復帰運動を展開していたころです。あれだけのことをしたのだから、厳しい顔をしているね。今になって思うのは、よくやったもんだなと。

アメリカ軍の統治下、本土との自由な往来が禁じられた奄美群島。深刻な食糧難で人々の暮らしは困窮を極めました。

苦しい生活の中、人々は日本への復帰を求めて立ち上がります。奄美群島の各地でデモ行進や集会が行われました。
当時20代だった田袋さんも、母間地区の青年団副団長として、島じゅうを回って運動への参加を呼びかけました。
田袋𠮷三さん
「日本人だから日本に帰ろう」「一致団結して頑張りましょう」と島の皆さんに呼びかけながら、トラックに発電機とマイクを積んで、あちこち回りました。反応はものすごかったですよ。マイクの声が聞こえたら外に出てきて手を振ったり、万歳したりして、みんな応援してくれました。

島ぐるみの復帰運動。20万の奄美の人たちの思いはただひとつだったと言います。
田袋𠮷三さん
われわれは日本人だから、どうしても早く日本に帰りたい。復帰したい。運動をすれば何とかなると。あれほどまでに奄美がまとまったことはないでしょうね。
厳しい統制の中で人々を鼓舞した“奄美のガンジー”
一方で、アメリカ軍はこうした活動を抑え込み、中には逮捕された人もいました。共産主義勢力の増長につながると警戒していたのです。田袋さんも警察に「組織の一員か」などと調べを受けたことがあったと言います。

厳しい言論統制の中、田袋さんたちの支えとなったのが、地元・徳之島出身で復帰運動を率いた詩人の泉芳朗でした。

非暴力・不服従を貫き、“奄美のガンジー”と呼ばれた泉。“断食祈願”と名付けたハンガーストライキに入り、団結を呼びかけました。

田袋さんもその知らせを聞き、仲間とともに“断食祈願”を行いました。“復帰がかなうまで最後まで闘い続ける”。心をひとつにしたと言います。
田袋𠮷三さん
われわれの声を聞いてくれという一心でした。“復帰”を勝ち取らなきゃいけない。命がけで一生懸命でしたよ。頑張ろうというみんなの気持ちがひしひしと伝わってきました。みんな思いはひとつだなという感じでした。
復帰運動の記憶を後世に

奄美の人たちの運動は、やがて、日本の世論をも動かしていきました。当時のニュースでも「日本に返して下さいと、都内の盛り場では署名請願運動が行われています」と伝えています。

そして、ついに日本への復帰が決まります。
その知らせを聞いた瞬間を、田袋さんは今も鮮明に覚えていました。

田袋𠮷三さん
言葉で表せないくらいうれしかったです。苦労が実った。やったという気持ち。その瞬間は何とも言えないです。今でも沸いてくる思いがありますね。

復帰から70年。ともに闘った仲間の多くが、この世を去りました。田袋さんは、復帰運動の記憶を、時代を超えてつないでいってほしいと考えています。
田袋𠮷三さん
印象に残っているのは、奄美がひとつになれたということと、復帰への執念です。苦しい中から今の世の中ができたのだから、今の世の中のありがたさをしみじみ感じてもらいたいです。
夢を遂行していく気持ちやみんながひとつになれるという目標を作ったほうがいいと思います。今の若い人たちには、自分の意志を貫くために頑張ってもらいたいですね。