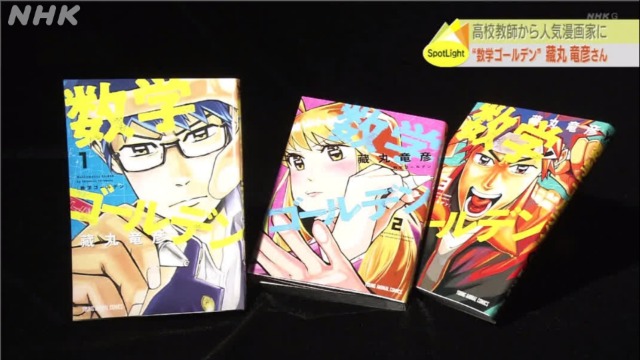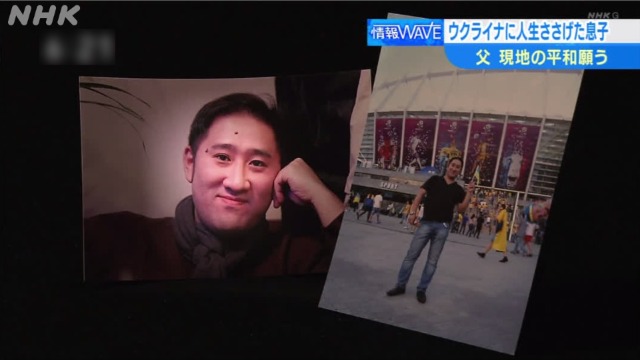”充実”の鹿児島の火山観測体制 その現在地と死角
- 2022年06月03日

充実しているとされる鹿児島の火山の観測体制。ただ近年、その隙を突くような事態が相次いでいます。背景に何があるのか、実情を探りました。
(鹿児島局記者 津村浩司)
いま日本で一番噴火活動が活発な火山へ

私(津村)が向かったのはトカラ列島にある火山島、およそ80人が暮らす諏訪之瀬島です。過去に全島民が避難したことがあり、66年前からは毎年噴火が発生。おととし10月以降は特に活動が活発化しています。

昼夜を問わず続く噴火に、島の人たちは不安を募らせています。

「噴火の音、それから空振は頻繁にあるので、そのときにはやっぱり怖いと感じます」

「噴火したときにはいきなりどーんという音、それからちょっと長くゴロゴロゴロという雷鳴みたいな音もしますよね。長年住んでいる私も、ここまで活発なのは初めてです」
夜にばかり出される“警報”のなぜ
この間、諏訪之瀬島では4回「火口周辺警報」が出されました。噴火警戒レベルを引き上げ、警戒が必要な範囲を広げる情報です。
ただ、私は取材する中である違和感を覚えました。警報は、住民が行動しやすい昼ではなく、なぜか夜にだけ発表されていたからです。

実は私は、噴火で被災した経験があります。2000年、伊豆諸島の三宅島で起きた噴火です。
いまほど情報が整備されていなかった当時。避難のタイミングに戸惑いながら、大量の火山灰などが降る中、避難所へ移動しました。
身をもって感じた情報の重要性。それが、どのように出されているのか確かめることにしました。
火山観測の現場は

県内の火山を監視しているのが、鹿児島地方気象台の「火山現業室」です。24時間体制で2人が常駐し、監視カメラや観測機器を駆使して火山の状態を解析。観測データが基準を超えた場合、警報を出して噴火警戒レベルを引き上げます。
基準のひとつになっているのが、大きな噴石の飛散距離です。

分析は監視カメラの映像と専用のソフトで行います。画面上で噴石の着弾地点をクリックすると…。
火口からの距離を自動で算出する仕組みです。日中は、粉じんが上がることで着弾地点を判別します。
夜間に相次いだ発表の背景
ただ、思わぬ弱点もあります。草木のある場所では粉じんが上がらず、確認が難しい場合もあるというのです。

一方で夜間は高温の噴石が光るため、粉じんがなくても軌跡を追いやすくなります。このため、諏訪之瀬島では警報が夜間に集中していたのです。

鹿児島地方気象台 小窪則夫火山防災官
「監視カメラが多い火山であっても、大きな噴石の飛散をもれなく追跡するには、カメラの死角などもあって限界があると考えている。現地調査、聞き取り調査による現地の情報によって早急に状況把握に努めているところだ」
“国内屈指”の桜島でも露呈する観測の難しさ
観測をめぐるさまざまな課題は、去年桜島でも浮き彫りになりました。
地下に3本の観測坑道が張り巡らされ、国内屈指といわれる観測体制。10万分の1ミリというわずかな地盤の変化を捉える「伸縮計」や、高感度の監視カメラも島の周囲にいくつも置かれています。

ところが去年4月25日、午前1時9分に爆発的な噴火が発生。
気象庁はその後、火砕流が1点8キロ流れ下ったと発表し、午前2時前に噴火速報を出しました。噴火の発生を伝え、即座に身を守る行動を取るよう呼びかける情報ですが、発表は噴火の43分後でした。

さらにその後、火砕流ではなく、風下に流された噴煙の一部だったことも判明しました。
カメラの機能に課題が
こうした発表の遅れは、なぜ起きたのか。
数百度以上にもなる高温が特徴の火砕流。ところが撮影した監視カメラには、赤外線で温度を測る機能がありませんでした。当時の性能では速やかに正確な判断をすることができなかったのです。

専門家「影響範囲の即時把握は十分でない」
長年にわたって、桜島や諏訪之瀬島の研究を続ける京都大学の井口正人教授は、噴石や火砕流などの影響範囲を即座に把握する体制はまだ十分でないと指摘します。


京都大学 井口正人教授
「従来の観測というのは、噴火そのものの発生の把握、あるいは噴火発生の予測に役に立つようなデータを取得するところに主眼が置かれてきた。影響範囲が即座に把握できるような監視体制というのもやはり必要で、その意味で言うとまだ足りない部分がある」
あらためて課題を突きつけた桜島や諏訪之瀬島の噴火。
それが火山観測の現在地です。

「噴火の規模を、その前兆現象から評価していくようなところはほとんどの火山でできていない。検証というのがなかなかしづらいというところにある、そういうところで、火山の噴火の難しさはあるんだろう」
取材後記
観測や予測の限界を認識した上で、災害にどう備えていくべきか。それを考えていくことは非常に重要です。
ただ今回の一連の取材で、そうした現状認識はまだまだ浸透しきっていないとも感じました。
目の前にある課題を今後もつぶさに取材して、防災のために伝え続けていきたいと思います。