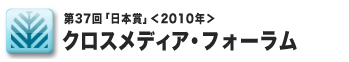
2008年以降、「日本賞」は世界の教育現場の急激なメディアの変化や多様化に伴いテレビ番組だけでなく、ウェブ、ゲームなど、教育的な意図をもって制作されたオーディオビジュアルコンテンツ全般にその審査の対象を広げました。ミート・ジ・エキスパーツはまさにその変遷期に生まれたイベントで、さまざまなコンテンツの教育的効果をプロの目から考察していきます。

Session1 映像のリアリティとは?〜多様性と相対性をめぐって〜
【パネリスト】
 |
藤幡正樹
メディアアーティスト、 東京藝術大学大学院映像研究科長 |
 |
豊田誠 アーキテクト〔システム、認知〕 |
 |
吉村司
株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 |
藤幡正樹氏をモデレーターに、豊田誠、吉村司両氏の話を交え映像の現在へ一石を投じるディスカッションが行われた。
吉村氏は、ガーナの村々で200インチハイビジョンテレビモニターを用いサッカーの試合中継を上映した際の記録映像"Power to the People"を紹介。テレビ体験の稀有な人たちにとってはメディアの原体験に、我々にとってもテレビメディアを改めて考える機会になったのではないかと話した。次に、全包囲(パノラマ)カメラを使ったプロジェクトを紹介し、撮影時には予測不可能なユーザーの振る舞い等の体験談により、この新しいメディアがこれまでのリニア(継時的)な時間感覚とは異なる時間体験を創り出す可能性があると語った。
藤幡氏は、異なった場所と時間での記録が画期的な方法でまとめられた、GPSと動画映像を用いた作品"Simultaneous Echoes"を上映。デジタル情報をベースに創作活動を行うことで、同じ内容の作品をギャラリーや劇場など様々な場のメディアに応じ、異なった形態のコンテンツに出力できる可能性を提示した。また、自身はこれまで数多くのインタラクティブな作品を制作してきたが、むしろリニアの表現の方が、人にとって読み取り易いのではないかと問題提起した。
豊田氏は、かつて遺伝的・先天的とされてきた人間の認知が、むしろ環境に依存した後成的なものであり、意識と無意識は疎結合状態で共存し並列に働くが、人間の行動の主導権を握っているのは無意識の方だと語った。さらにモノクロは記憶の反応を、カラーは感情を呼び起こす性質があるなど、視覚機能についての話を軸に自身の認知研究の成果を述べ、教育的メディアで新しいテクノロジーを使用する際は、どのように身体的体験と連鎖させ、認知の仕組みとの整合性を図るかの十分な検討を求めた。
これらを踏まえ「メディアの受容にも環境依存が含まれており、環境による差別化が起きている」「偶発的なハプニングなどによって無意識から立ち上げられた意識でこそ顕在認知が可能になり、リアリティを作り出す。分散した意識には何も伝わらない」「現代のように新しいメディアが溢れている時は、そのメディアの本質を解き明かすような作品が出て来なければ、次の段階に向かえない。それらの検証を経て私たちはメディアを理解するのではないか」などの意見が述べられ、ディスカッションは大きなインパクトとともに終了した。
吉村氏は、ガーナの村々で200インチハイビジョンテレビモニターを用いサッカーの試合中継を上映した際の記録映像"Power to the People"を紹介。テレビ体験の稀有な人たちにとってはメディアの原体験に、我々にとってもテレビメディアを改めて考える機会になったのではないかと話した。次に、全包囲(パノラマ)カメラを使ったプロジェクトを紹介し、撮影時には予測不可能なユーザーの振る舞い等の体験談により、この新しいメディアがこれまでのリニア(継時的)な時間感覚とは異なる時間体験を創り出す可能性があると語った。
藤幡氏は、異なった場所と時間での記録が画期的な方法でまとめられた、GPSと動画映像を用いた作品"Simultaneous Echoes"を上映。デジタル情報をベースに創作活動を行うことで、同じ内容の作品をギャラリーや劇場など様々な場のメディアに応じ、異なった形態のコンテンツに出力できる可能性を提示した。また、自身はこれまで数多くのインタラクティブな作品を制作してきたが、むしろリニアの表現の方が、人にとって読み取り易いのではないかと問題提起した。
豊田氏は、かつて遺伝的・先天的とされてきた人間の認知が、むしろ環境に依存した後成的なものであり、意識と無意識は疎結合状態で共存し並列に働くが、人間の行動の主導権を握っているのは無意識の方だと語った。さらにモノクロは記憶の反応を、カラーは感情を呼び起こす性質があるなど、視覚機能についての話を軸に自身の認知研究の成果を述べ、教育的メディアで新しいテクノロジーを使用する際は、どのように身体的体験と連鎖させ、認知の仕組みとの整合性を図るかの十分な検討を求めた。
これらを踏まえ「メディアの受容にも環境依存が含まれており、環境による差別化が起きている」「偶発的なハプニングなどによって無意識から立ち上げられた意識でこそ顕在認知が可能になり、リアリティを作り出す。分散した意識には何も伝わらない」「現代のように新しいメディアが溢れている時は、そのメディアの本質を解き明かすような作品が出て来なければ、次の段階に向かえない。それらの検証を経て私たちはメディアを理解するのではないか」などの意見が述べられ、ディスカッションは大きなインパクトとともに終了した。
Session 2 最先端メディア、従来のメディア
〜教育コンテンツ制作における効果的な利用〜
〜教育コンテンツ制作における効果的な利用〜
【パネリスト】
 |
アヴァ・カーボネン
リール・ガールズ・メディア/カナダ |
 |
カッレ・フルスト 上海万博 ノルウェー 文化プログラム統括/ノルウェー |
 |
佐藤隆善
アプライド・リサーチ・アソシエイツ、 |
一次審査委員を務めた3人のエキスパートが、今年のエントリーの中で議論の的となった作品を例に、今後の教育コンテンツの方向性について意見交換を行った。
一次審査で幼児・児童向けカテゴリーのチームリーダーを務めたカッレ・フルスト氏は、「読み書きの力を磨け!」を取り上げ、「世界中のインタラクティブなメディアやアーカイブを使用する良い例だ」と評した。また今年は、リニアとノンリニアの両方で同じ題材のエントリーが多かったことについて、メディアの融合が今後さらに進むであろうと予測し、その参考となる作品として「戦争についての13のシリーズ」を紹介した。次に、一次審査で生涯教育・福祉教育カテゴリーのノンリニア・アドバイザーを務めた佐藤隆善氏を中心に、社会のタブーやデリケートなテーマを取り上げる際のアプローチの難しさが話し合われた。福祉教育カテゴリーの「薬物の後遺症」や生涯教育カテゴリーの「問題行動への挑戦」を好例とし、教育的役割を達成し、エンターテイメント性やメッセージ力をあわせ持つためには、ノンリニア作品においてもしっかりとした構成が必要であることが確認された。また、これまではテレビ番組の延長線で制作されたウェブやゲームのエントリーがほとんどだったが、これからはウェブやゲーム発のリニア作品が出てくる可能性があると「日本賞」の今後の展開について語り合った。
青少年カテゴリーのチームリーダーで、テレビ番組や数多くのマルチメディア作品の制作に携わってきたアヴァ・カーボネン氏は、「古い題材をいかに新しい形で見せるか」という点を検証。その好例として「ハンナのかばん オンライン」と「Web版『エリンが挑戦!
にほんごできます。』」を紹介し、構成や表現を練り上げることと文化的視点をインタラクティブな展開に組み入れることの大切さを議論した。
後半、新しいメディアやテクノロジーは教育コンテンツを向上させるかという問いに対し、「子どもたちはクロスメディアの中で、メディアが何であるか気にすることなく、新しいテクノロジーを享受している」「制作者にとっては、オーディエンスのニーズを探り、質の良いコンテンツ、提供の仕方を考えていくことが大切である」「今年のエントリーの傾向からも、テレビ番組とウェブなど新しいメディアを連動させた企画が増えていくことが予想され、それらの企画を包括的に検討していくことが、『日本賞』の課題の1つとなっていくだろう」と語った。
一次審査で幼児・児童向けカテゴリーのチームリーダーを務めたカッレ・フルスト氏は、「読み書きの力を磨け!」を取り上げ、「世界中のインタラクティブなメディアやアーカイブを使用する良い例だ」と評した。また今年は、リニアとノンリニアの両方で同じ題材のエントリーが多かったことについて、メディアの融合が今後さらに進むであろうと予測し、その参考となる作品として「戦争についての13のシリーズ」を紹介した。次に、一次審査で生涯教育・福祉教育カテゴリーのノンリニア・アドバイザーを務めた佐藤隆善氏を中心に、社会のタブーやデリケートなテーマを取り上げる際のアプローチの難しさが話し合われた。福祉教育カテゴリーの「薬物の後遺症」や生涯教育カテゴリーの「問題行動への挑戦」を好例とし、教育的役割を達成し、エンターテイメント性やメッセージ力をあわせ持つためには、ノンリニア作品においてもしっかりとした構成が必要であることが確認された。また、これまではテレビ番組の延長線で制作されたウェブやゲームのエントリーがほとんどだったが、これからはウェブやゲーム発のリニア作品が出てくる可能性があると「日本賞」の今後の展開について語り合った。
青少年カテゴリーのチームリーダーで、テレビ番組や数多くのマルチメディア作品の制作に携わってきたアヴァ・カーボネン氏は、「古い題材をいかに新しい形で見せるか」という点を検証。その好例として「ハンナのかばん オンライン」と「Web版『エリンが挑戦!
にほんごできます。』」を紹介し、構成や表現を練り上げることと文化的視点をインタラクティブな展開に組み入れることの大切さを議論した。
後半、新しいメディアやテクノロジーは教育コンテンツを向上させるかという問いに対し、「子どもたちはクロスメディアの中で、メディアが何であるか気にすることなく、新しいテクノロジーを享受している」「制作者にとっては、オーディエンスのニーズを探り、質の良いコンテンツ、提供の仕方を考えていくことが大切である」「今年のエントリーの傾向からも、テレビ番組とウェブなど新しいメディアを連動させた企画が増えていくことが予想され、それらの企画を包括的に検討していくことが、『日本賞』の課題の1つとなっていくだろう」と語った。