【ピョンチャンパラリンピックまで1年】選手からのメッセージ
2017年04月05日(水)
3月30日放送「ピョンチャンパラリンピックまで1年 冬のパラスポーツを楽しもう!」にご出演下さった3人の選手にあらためて意気込みをお伺いしました。
2017年04月05日(水)
3月30日放送「ピョンチャンパラリンピックまで1年 冬のパラスポーツを楽しもう!」にご出演下さった3人の選手にあらためて意気込みをお伺いしました。
2017年04月03日(月)
ご出演いただいた宇田川健さんに、番組収録後、お話をうかがいました。 【宇田川健/認定NPO法人COMHBO共同代表】精神障害のある人への情報提供などを行う。自身も統合失調感情障害で入院経験がある。
【宇田川健/認定NPO法人COMHBO共同代表】精神障害のある人への情報提供などを行う。自身も統合失調感情障害で入院経験がある。
――今回の《相模原事件を受けて 精神医療は今》にご出演されて、どのようなことを感じましたか?
兵庫の例としてもでていましたが、精神科医療ではどうしても力関係の中で、医師の力が大きいのです。これからは、普段の地域で暮らしている本来の自分のことを全く知らない人たちが、この人をどうしようかと、本人不在のまま入院中に計画が立てられ、それがずるずると地域の中でも継続されていくのは、とても恐ろしいと思っています。支援計画という名の地域での縛りを守ると同意しなければ、退院させないなどという事態が起きるのではないかと危惧しています。これは病院から地域へという流れを逆行させるものですし、そもそも地域という言動と行動の自由、こころの自由な場所が、もう地域ではなくなってしまい、地域が支援計画という名のついた縛りのある場所になってしまうのではないかと、不安に思います。そのときには、地域はもう本来の意味の地域ではなくなってしまうのではないでしょうか。今回の精神保健福祉法の改定案に出されている病院から地域へという流れは止めないという文章は二重の意味で空文化されていると思います。
2017年04月03日(月)
ご出演いただいた松本俊彦さんに、番組収録後、お話をうかがいました。 【松本俊彦/精神科医】国立精神・神経医療研究センター 薬物依存研究部。相模原事件再犯防止策検討チームの構成員。
【松本俊彦/精神科医】国立精神・神経医療研究センター 薬物依存研究部。相模原事件再犯防止策検討チームの構成員。
――今回の《相模原事件を受けて 精神医療は今》にご出演されて、どのようなことを感じましたか?
今回、宇田川さんのお話を聞いたり、VTRを見たりするなかで、以下のようなことを考えました。それは、これまでの医師・医療主導の精神保健的支援から、様々な職種から構成される地域主導の精神保健的支援の必要性です。前者では、ともすれば「症状・病状」ばかりが注目されてしまいますが、後者では、「生活への満足度や生きがい、日々の充実感」こそが重要になります。
そして、その際、強調されるべきは、支援チームのなかに必ずピアスタッフを加えることです。ピアスタッフは援助者の側面を持ちつつも、当事者でもあります。当事者スタッフは、どんなに優れた援助者にも決して提供できないものを提供することができます。
それは「希望」です。
自分の病気を受け入れられず、治療や服薬、診断名まで拒む方の多くが、そうした者を受け入れた「向こう側」に希望が見えないと感じています。その「向こう側」に想像される生き方が少しも魅力的ではないと感じています。
ピアの人たちは、「そんなに悪くないし、まあ、ときにはつらいこともあるけど、けっこう日々を楽しんでいるよ」と伝えることができるように思います。
ぜひこれからの地域精神保健的支援は、まだ苦しんでいる当事者の方々に「希望」を運んでくれるものとなるべきだ。そう思いました。
2017年03月31日(金)
 JR東日本が運行している「生きる支援トレイン」の車内に流れている動画「生きるためのダンス」。動画を制作したディレクター・後藤 怜亜からのメッセージです。
JR東日本が運行している「生きる支援トレイン」の車内に流れている動画「生きるためのダンス」。動画を制作したディレクター・後藤 怜亜からのメッセージです。
「生きるためのテレビ」は、2014年から、ハートネットTVのディレクターがバトンをつないで、「死にたい」「生きるのがつらい」という声に耳を傾けてきました。いただいた投稿を読む中で、「死にたい」という気持ちは、何か決定的・圧倒的な要因がある特別な感情としてではなく、日々の些細な傷付きや苦しさ、または「何もない」日常への不安から、コップに溜まった水がたった1滴の揺らぎで溢れだすように、誰にでも起こり得るものだと、私は思いました。
私個人にとってもその感情は、切実で身近な揺らぎとしていつもそばにありました。10代の頃に経験した家庭のいびつさ、学校での「みんなと違う」自分の存在。私にとっては、そのトンネルの奥深くに、か細い糸のような光を与えてくれたのが、美術、音楽、そして映画でした。それらと、それらを通した出会いが無ければ、今の自分はありませんでした。その道の途中でたまたま、放送という世界に流れ着きました。
声に出せない言葉。喉の奥につっかえて、出てこない。頭の中にいつもあるのに、声として輪郭を与えることができないその感情の塊を、言葉ではない手段でかたちにしたい。
そう思った時、力を貸してくれたのはやはり、美術、音楽、映画の世界の人々でした。ダンサー・振付家のハラサオリさん、映像作家の佐々木友輔さん、作曲家の田中文久さんと一緒に、それぞれが抱えるバックグラウンドを持ち寄って、Aさんが寄せて下さったメールが持つ空気感に、柔らかな輪郭を与えようと試みたのが「生きるためのダンス」です。
通勤する電車の中で。1人でいる部屋の中で。誰かの心で、コップの水が溢れだしそうになった時。「生きるためのダンス」が、声に出せない感情の塊を、せめて何かのかたちで表現してみる、ほんのひとさじ分の勇気になってくれたら、と願っています。
 角銅真実(歌) 角銅真実(歌)「この世のはじっこに」 |
 田中文久(音楽) 田中文久(音楽)「手のひらの匂いがするような」 |
 佐々木友輔(撮影・編集) 佐々木友輔(撮影・編集)「見知らぬ誰かのもとへ」 |
 ハラサオリ(ダンス) ハラサオリ(ダンス)「遠い誰かのこころに」 |
2017年03月29日(水)
 JR東日本が運行している「生きる支援トレイン」の車内に流れている動画「生きるためのダンス」。動画制作に関わっていただいた 振付・ダンス:ハラサオリさんからのメッセージです。
JR東日本が運行している「生きる支援トレイン」の車内に流れている動画「生きるためのダンス」。動画制作に関わっていただいた 振付・ダンス:ハラサオリさんからのメッセージです。
自殺に関する相談を寄せたり、実際に行動へ移してしまうのは圧倒的に10代が多いという統計には、経験上納得せざるを得ないものがあります。私自身、幼少期の時点で周りと上手くコミュニケーションが取れず毎日の生活が苦痛で仕方ありませんでした。子供の自分が、家と学校の2点を結ぶ線の世界に自力で逃げ場を作ること、さらに逃げる自分を肯定することは、いま考えても不可能だったと思います。
しかし、このような切迫した状況が大人にとっても珍しくなくなっているということも、特にここ数年の間に日常レベルで感じるようになりました。私は運良く(ある面では)寛容な、表現の世界に救いを見つけて生きていくチャンスをもらいました。それでも頭にこびりついた自己否定の記憶や息苦しさがフラッシュバックしてしまうような何かが、やはりこの社会には漂っているように思います。
今回のプロジェクトに関わる上で強く意識したのは「誰かの為になろうとしないこと」でした。代弁や救済を背負うのではなく、Aさんの身から切り出されたことばが私の身体を通過したときに生まれる「ゆらぎ」のようなものを捉えて残すことが、自分に与えられた役割だったと思っています。逆に言えば、普遍化できない「自殺」にまつわる事実や感情と向き合うには、完全に自分事として取り組む以外にできることはありませんでした。これは「私が生きるためのダンス」であり「誰かが生きるためのダンス」でもある、そんなことが伝わればいいなと思います。
 ハラサオリ
ハラサオリ
 角銅真実(歌) 角銅真実(歌)「この世のはじっこに」 |
 田中文久(作曲) 田中文久(作曲)「手のひらの匂いがするような」 |
 佐々木友輔(撮影・編集) 佐々木友輔(撮影・編集)「見知らぬ誰かのもとへ」 |
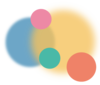 後藤 怜亜(ディレクター) 後藤 怜亜(ディレクター)「ほんのひとさじ分の勇気」 |
2017年03月28日(火)
 JR東日本が運行している「生きる支援トレイン」の車内に流れている動画「生きるためのダンス」。動画制作に関わっていただいた 撮影・編集:佐々木 友輔さんからのメッセージです。
JR東日本が運行している「生きる支援トレイン」の車内に流れている動画「生きるためのダンス」。動画制作に関わっていただいた 撮影・編集:佐々木 友輔さんからのメッセージです。
ひとが死にたくなる理由や生きたくなる理由はさまざまで、とても一般化できるものではないぞと当たり前のことを考えて、それでもなお「生きるためのダンス」の撮影を引き受けようと決めたのは、誰がなんのためにやっているのかもよく分からないような表現に自分自身が救われた経験が幾度もあったからです。
たとえば今回のダンス動画にしても、Aさんはどのような気持ちであのテキストを書いたのか、ハラさんはそれをどのように解釈してあの振り付けをつくったのか、想像することはできても、ほんとうのところはなにも分かりません。でも、その分からなさと向き合いながらカメラを回していると、自分とは別の人間がたしかにそこにいることが感じられて、なにかとてつもなく大きなものがその向こうに広がっているように思えて、もっと知りたい、もっと見たいという気持ちになる。
そして、全力でそれについて考えだしたら、今度は時間がいくらあっても足りなくなるのです。テキストからダンスへ、ダンスから動画へとつながってきたバトンが見知らぬ誰かのもとに届き、そこでまた新たな感情や、新たな表現が続いていく。そんなことがあれば良いなと思います。
 佐々木 友輔 (ささき ゆうすけ)
佐々木 友輔 (ささき ゆうすけ) 角銅真実(歌) 角銅真実(歌)「この世のはじっこに」 |
 田中文久(作曲) 田中文久(作曲)「手のひらの匂いがするような」 |
 ハラサオリ(ダンス) ハラサオリ(ダンス)「遠い誰かのこころに」 |
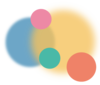 後藤 怜亜(ディレクター) 後藤 怜亜(ディレクター)「ほんのひとさじ分の勇気」 |
2017年03月28日(火)
 JR東日本が運行している「生きる支援トレイン」の車内に流れている動画「生きるためのダンス」。動画制作に関わっていただいた 歌:角銅真実さんからのメッセージです。
JR東日本が運行している「生きる支援トレイン」の車内に流れている動画「生きるためのダンス」。動画制作に関わっていただいた 歌:角銅真実さんからのメッセージです。
この世のはじっこに、指一本引っ掛けてぶらさがっている
ひっかけた一本の指先の部分だけで、生きている この世に
もうやめたい
この指をほどけば、とても気持ちがいいかもしれない。
楽になれるかもしれない。
でも、引っ掛けた指先の接点は 時折熱を持ち
私は見たことのない色を見る
その熱は私を撫で、私を照らし、私を驚かせる
ゆるされたような気持ちになる、一瞬でも
そんなとき、私
どうか、この世と滲みたい。生きていたい。
祈るみたいに そう思う
そんなとき、
全身が金色の嬉しいで満ちる。
その いつかの遠いとおいとおい金色を
とおくとおくとおく反芻しながら 今日も息をしている
この世のはじっこに、指一本引っ掛けてぶらさがったまま
 角銅 真実 (かくどう まなみ)
角銅 真実 (かくどう まなみ)
 佐々木友輔(撮影・編集) 佐々木友輔(撮影・編集)「見知らぬ誰かのもとへ」 |
 田中文久(作曲) 田中文久(作曲)「手のひらの匂いがするような」 |
 ハラサオリ(ダンス) ハラサオリ(ダンス)「遠い誰かのこころに」 |
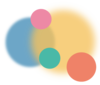 後藤 怜亜(ディレクター) 後藤 怜亜(ディレクター)「ほんのひとさじ分の勇気」 |
2017年03月28日(火)
 JR東日本が運行している「生きる支援トレイン」の車内に流れている動画「生きるためのダンス」。動画制作に関わっていただいた作曲:田中 文久さんからのメッセージです。
JR東日本が運行している「生きる支援トレイン」の車内に流れている動画「生きるためのダンス」。動画制作に関わっていただいた作曲:田中 文久さんからのメッセージです。
どのような音楽を作るべきか当初は色々悩みましたが、最初のミーティングのときにディレクターの後藤さんの思いを受け私が語った(らしい)「手のひらの匂いがするような」音楽を目指しました。
手のひらの匂いみたいな、特別良い匂いではないけど、「生きてるんだなあ」って思えるような、ちょっと客観的にわかるような、日常の繊細さ、ざらつき、質感、そういったものを大切にし、丁寧に作曲しました。
私は小さい頃から周りに上手く馴染むことができず、死にたい気持ちと近くに居ることが多くありました。私の場合は、出口を探したり、逃げたり、という発想そのものが無いような状況でした。そのときに助けてくれたのが音楽で、音楽に没頭している時はいろんなことを忘れていられました。そんなこんなで、どうにか今まで生きてきています。
「みんなさあ、『死にたい』とか普通に思ったことあるよね」とかって自然に言えるのが前提になって、死にたい思いと自然に共存して生きていける社会になっていったらいいなあと思います。
 田中 文久 (たなか ふみひさ)
田中 文久 (たなか ふみひさ) 佐々木友輔(撮影・編集) 佐々木友輔(撮影・編集)「見知らぬ誰かのもとへ」 |
 角銅真実(歌) 角銅真実(歌)「この世のはじっこに」 |
 ハラサオリ(ダンス) ハラサオリ(ダンス)「遠い誰かのこころに」 |
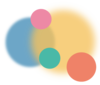 後藤 怜亜(ディレクター) 後藤 怜亜(ディレクター)「ほんのひとさじ分の勇気」 |
2017年03月07日(火)
 WEB連動企画"チエノバ"コメンテーターの荻上チキです。
WEB連動企画"チエノバ"コメンテーターの荻上チキです。
2016年、芸能人やスポーツ選手の薬物問題についての報道が相次ぎました。
中には薬物依存症への偏見や誤解を助長する内容も少なくないと感じました。
そこで、薬物報道のあり方について、専門家や当事者の方々と議論を重ね、次のようなガイドラインを作りました。
2016年08月02日(火)

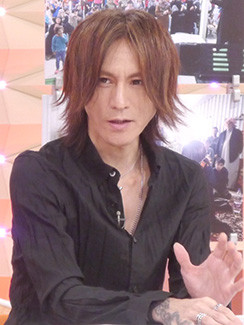
『シリア難民であり障害者である私たち』にご出演されたSUGIZOさんにメッセージをいただきました。
《SUGIZOさんプロフィール》
LUNA SEA、X JAPANのギタリスト、ヴァイオリニストであり作曲家。今年3月にヨルダンのシリア難民キャンプを訪問した。
――SUGIZOさんがこのような社会問題に目が行くようになったのは、娘さんの誕生がきっかけだそうですね。
今年娘が成人したので20年前、だから90年代後半からです。それまでは絵に描いたような荒れたロックンローラー的な生活で、どちらかと言えばネガティブなタイプでした。でも、自分の子どもが生まれて、だんだん大きくなっていって、僕とコミュニケーションがとれるようになったときくらいかな、娘だけじゃなく、娘の友だちも同じように大切に思えてきたんです。すると、その年代の子どもたち全員が愛おしくなって、次は海外の子どもたちが愛おしくなって。そうなると難民の子どもたち、当時ならアフリカの飢餓に苦しむ子どもたちに意識がシフトしていきました。成人できないうちに命を落とすような世界で生きている子どもがたくさんいる……。だから、目が行くようになったきっかけは子どもたちの存在ですね。どうすればこれからの未来を担う彼ら彼女らがより安全に、健全に、幸せに成長して生きていける世界になるか。90年台後半からそういう意識にフォーカスするようになりました。