17年ぶり快挙!ベネチア監督賞 黒沢清監督が語る

べネチア国際映画祭で、黒沢清監督が、「スパイの妻」で監督賞を受賞。日本の監督の受賞は北野武監督以来、17年振りの快挙だ。作品は太平洋戦争の直前に国家機密を偶然知ってしまい、正義のために世間に公表しようと暗躍する男性と、その妻の物語。黒沢監督をスタジオに招き、これまで現代を舞台にホラーや家族の物語などを中心に撮ってきた監督が、今回なぜ激動の時代を選んだのか、そして描きたかったテーマなど、作品にこめた思いに迫る。
出演者
- 黒沢清さん (映画監督)
- 武田真一 (キャスター)
ベネチア銀獅子賞・黒沢清監督が語る
武田:今回制作された映画「スパイの妻」。監督ご自身はいろいろな評価・評判をお聞きになっていると思いますけれども、何がよかったと聞いてらっしゃいますか?
黒沢さん:正直言って、自分ではよく分からないんですけども。なんか僕が1つ聞いた意見ですと、それは、こういうテーマを扱った、この時代の物語の日本映画というのがあるとは知らなかったと、大変驚いたという意見を聞いて、それはうれしいことだなと思いました。つまり戦争、戦時下の物語ですし、戦争という非常に重たいテーマが背後にあるんですけれども、物語の構造はサスペンスであるとかメロドラマといった娯楽映画、ジャンル映画の構造になっていて、はらはらドキドキしながら楽しく見ることもできる。でも、重たいテーマも同時にあるという、そういうのって西洋では無くはないと思うんですけど、あんまり日本のこういう時代を扱った映画で、これまでなかったんじゃないかと思って、そのことは意識しながら創っていました。それが、ベネチアに来た海外の方にも、そのことは伝わったのかなと思って、それはうれしく思いましたね。
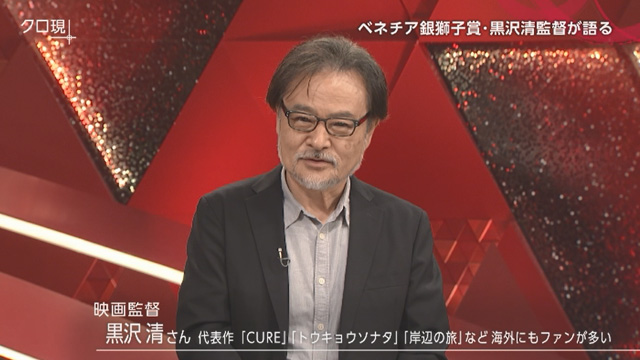
「スパイの妻」世界はどう受け止めた?
「スパイの妻」は、黒沢監督が初めて挑戦した歴史サスペンス。戦時下の日本が舞台です。
太平洋戦争、前夜。偶然、日本軍の恐ろしい行為を知ってしまった貿易商と、その妻の物語です。社会全体が大きく戦争へと傾く中、高橋一生さん演じる夫は、みずからが信じる正義のため、国家機密を公表しようと画策します。愛する夫と国家のはざまで翻弄される妻、聡子を蒼井優さんが演じます。
夫の思いを遂げるため、さまざまな手段を講じる妻。そこに迫る憲兵隊の影。スリリングなサスペンスを通して、国家と個人、そして時代のうねりの中で生きる夫婦の関係を描いた作品です。
黒沢監督は、すでに20年以上前から、日本を代表する映画作家として世界の映画関係者から支持されてきました。商業映画デビューは1983年。ピンク映画に始まり、ヤクザものから家族をテーマにしたものまで、ジャンルを超えた映像作品は50本以上にも及びます。

ホラー映画の鬼才として知られ、2001年に「回路」が、カンヌ国際映画祭で国際批評家連盟賞を受賞。すべての作品に共通するのが、娯楽性の中に際立つ独特な映像表現と世界観。映画界の巨匠、黒澤明にちなんで「第二のクロサワ」と内外のファンから称されてきました。

今回の受賞作「スパイの妻」を鑑賞したベネチアの審査員からは、称賛の声が相次ぎました。
審査委員
「私は黒沢監督の映画が大好きなの。彼はホラー作品から始まって、今は彼ならではのやり方で現実社会を描く、本当にすばらしい監督だと思うわ。」

審査委員 クリスティアン・ペツォールト監督
「私はこの作品が大好きでした。なぜなら、オペラ的なリズムと画面作りで政治ドラマを描いている。1930~40年代の伝統的な世界を現代のスタイルで表現している。」
「スパイの妻」なぜ戦時下の日本を舞台に?
武田:監督ご自身は、この戦争の時代というのをどう捉えて、どういうふうに描くべきだというふうに考えてらっしゃったんでしょうか?
黒沢さん:やはり、この時代の状況というのは、もちろん想像するしかないんですけれども、非常に自由に生きようとする個人にとっては、つらい世の中だったんだろうと思うんですけれども。その中で、それでも自分の幸福とか、自分自身の欲望を追求しようとした人は必ずいたわけで、そういう人たちと社会は、当時は激突したんだろうと思うんですけど。そういう個人の自由でありますとか、社会との軋轢(あつれき)といったようなものは、多分どの時代でも当てはまる普遍的なテーマだと思いますし、そういうことをベースにした娯楽映画ですね。アクションであったりサスペンスであったり、そういうものはいくらでも創ることは可能だと思っていますし、そういうものを楽しく見ていただいて。で、重たいテーマは決して薄まるはずはない。すごく楽しかった、はらはらドキドキ見たと同時に、ものすごく重い何かを受け止めてくれたら、映画というのは本当にいいものだなと、かねがね思っていましたので。
戦時下の日本 現代に通じるテーマは?
武田:「今の時代にも通じる」とおっしゃいましたけれども、それは具体的にはどういうことでしょう?
黒沢さん:これ、結構誤解を生みそうなので正確に言いますと、僕は、社会と個人の関係性を描きたいために映画を創ってるわけでは全然ないんですよ。ただ、どんな物語を語ろうとしても、それを生身の人間が現代、あるいは別な時代であっても、ある状況の中で人間が動いていくという物語を考えていくと、それはホラーであっても、例えば、仮にコメディーであっても、必ず社会と個人がどこかでぶつかってしまうという状況が必ず出てくるんですね。
皆さん、やっぱり自分の欲望、自分の幸せを追求していこうとすると、どこかで、「それはやっちゃいけないよ」とか「それをやるのはとっても大変よ」とか、「やりたいなら、まずお金もうけてからやりなさい」とか、さまざまな社会の要請や圧力が加わって、幸福や自由というのは、どこかで押さえつけられてしまうなというのを実感していると思うんですね。
はっきり目に見えないから、表現としてはすごくそれが曖昧になってしまうんですけども、だから現代で物語を創るときに、これは絶対に避けて通れない、テーマというよりも通過儀礼みたいなものだと僕は思っています。

武田:そうした黒沢さんの数々の作品、本当に深いテーマがあるんだなと今、実感しましたけれども、そういった作品を彩る手法ですね。一体、独特のこの黒沢ワールドの魅力の秘密はどこにあるんでしょうか。
黒沢映画 魅力の秘密は?
海外でも高く評価されてきた、黒沢映画の独特のスタイル。
まずは、1つの場面をカットを割らずに見せる「長回し」の手法。今回の「スパイの妻」でも要所要所に見られます。最も長いシーンは、主人公が夫に真実を迫る場面。1カットが5分間にも及びました。

もう一つ、黒沢ワールドを形作るのが、「光と影」。映画「岸辺の旅」では、光と影を巧みに使い、カンヌ国際映画祭のある視点部門で監督賞を授賞しました。
死んで幽霊になった夫と旅をしながら、生前は理解できなかった夫の優しさや人間性を見つけていく妻。作中、亡くなった人が霊となって登場する場面では、光と影が印象的に変化します。
「風」も、作品の重要な場面で必ず登場します。
“クロサワ”ワールド「印象的な長回し」
武田:大事なシーンが長い1カットで描かれることが多い印象があるんですけれども、そこは何か意識されたり、狙いがおありになるんでしょうか。
黒沢さん:撮影現場って、それなりに緊張するある1カットを撮っているときって…緊張するんですよ。「よーい、スタート」でカットが始まって終わるまで、ある持続した時間が、俳優はもちろんのことカメラマン、あるいはいろんなものを用意する小道具とか。全員が緊張するある瞬間なんですが、それを撮った後、適宜分かりやすいように編集してしまうと、撮影現場であれだけ緊張したのが薄まって、効率よく物事を説明することはできるんですけど、本当に効率と説明に全部変換されてしまう。
映画というのは長さが決まっていますから、その効率のいい説明というのは確かに必要なんですが、なるべく頑張って、撮影現場での「よーい、スタート」からカットまでの、持続するあの緊張した時間というのを、何とかそのまま、そのままの形でお客さんにも届けることができないもんかなというのは、常々思っているところです。撮影現場で1分あったものをそのまま見せれば、見てる方も同じ1分間ということで経験できるわけですから、それをそのまんま伝えたいと。

「光と影、そして、風」
武田:光や風というものを、非常に効果的に生かしている作品が多いように感じるんですが、これはいかがですか?
黒沢さん:なかなか鋭いとこを突いてきますね。おっしゃるように、光ないしは影というものと風というのは、僕にとって、映画表現をする上で無くてはならない、とても重要視しているものです。まさに、ここぞというときにあるものを見せる。あるいは、あるものをあえて見せない。場合によってはだんだん見せてくるとか、何か物事、重要な何かをどれだけ見せるか見せないかっていうのを、操るというと変ですけど、こっちで操作する、とても重要な光を当てなければ映らないわけですから。ただ、すべてを映すことが重要でもないわけですね。
まさに光を操って、こちらの語る強さをそこでコントロールしているつもりなんですが、ところが風というのは、くせ者で。映画ってフレームがあるんですけど。フレームの中が見えているんですけど、外側がどうなっているかっていうのは、誰にも分からないんですね。外側の何かが突然、画面の中に影響を与える。それが風なんですよ。だから、狙って扇風機で外から風を当てることもあるんですけど、僕が一番好きなのは多分、武田さんにとっても僕の映画を見ていただけたら印象に残ってるかもしれない風は、本当に自然に吹いた風なんです。それは本当に起こるんですね。
撮影していて、それまで閉じたフレームの中を見つめていた、これがこの世界なんだなと思っていたものが、何か、わあっと開かれるような、別の世界に連れていかされるような気持ちよさ。今まで「こうだろうな」と信じていたものが、全然違ったかもしれないと思う、ちょっとショックも含めた爽やかさみたいなものが風で、突然風が吹くことによって何か表現されている。本当に風が吹いたときは、やったぁと思いますね。そういう何か外部の力を呼び込んだという。
壊れていく“日常”
黒沢作品で繰り返し描かれるモチーフは、それまで平穏だった世界が静かに壊れ、変質していく様子です。
幽霊の出現によって、次々と周りの人々が謎の失踪をとげ始めたり。実は宇宙人がひそかに人の体に乗り移り、知らぬ間に社会を支配していたり。当たり前と思っていた社会の前提が突然壊れ、見る者の価値観を大きく揺さぶります。それこそが黒沢映画の持つ普遍性だと、映画監督の犬童一心さんは指摘します。
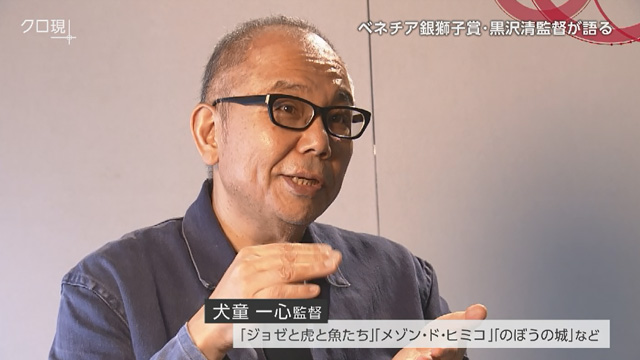
犬童一心監督
「日常が、何かこう、ちょっとずつ壊れはじめるんじゃないかっていう、その恐怖っていうんですかね、その不安っていうのが、誰もがどこの国の人も持っているんじゃないかと思うんですよ。自分たちで身をもって迫っているような映画に見えたりするわけじゃないですか。その時代の、そのときの現実を描いている映画として迫ってくるっていうんですかね。」
その大きく変質する世界の中で必死に生きようとするのが、1組の恋人や夫婦です。未曽有の危機や不条理な世界に翻弄されながら、主人公たちは、改めて互いの関係について深く見つめ直します。
武田:何かこう、日常が静かに崩れていく、壊れていく、そういう恐怖を描くということが多いように感じるんですけれども、黒沢さんが描きたい、あるいは一番お感じになる「怖い」と思う恐怖というのは、どういうことなんでしょうか?
黒沢さん:うーん。なかなか難しい質問で、いろんなものが怖いのですけれども、人並みに。
おっしゃるように、全く未知のものが、気が付いたらふっとものすごい近くにいたとか、あったという瞬間は、想像するとすごく怖いだろうと思います。日常生きていて、そういう目に遭うことはあまりないんですけれどもね、想像すると怖いですね。
何でそれが、全然知らないものが、突如ものすごく身近にある瞬間というのが怖く感じるのかというと、分かりやすい表現をすると、やっぱりそれは「死」、死ぬことのどこかメタファーといいますか、死というのも簡単にひと言で言えるようなものではないといいますけど、ひょっとするとそんなものはどこにもない。日常にそんな死の影など全くないと思って、ほとんどの人が生きてるかもしれませんけど、よく考えると次の瞬間、あすにも突如死が訪れるかもしれないわけですよね。何が起こるか分からない。
だから、ふと気付くとすぐ後ろに死が迫っているというのは、割と難しいですけども、人間が生きているという本質なのかもしれないなと。だからふと死を感じてしまったら、こんな恐ろしいことはないだろう。その瞬間から日常というのはガラガラと崩れて、僕らが信じていた日常というのは崩れていくのかもしれないなと思うと、それが一番恐ろしいかもしれませんね。
武田:そんな中で、私たちは今、大事だと気付いたこともあると思うんですよね。例えば身近な人との絆であったり、会いたい人にいつでも会えるという幸せであったり。
黒沢さん:僕が声高にそれをここで言える立場にはないのですけども、僕が実感しているのは、これは映画でも実は描くことなんですけれども、絆とか、そういった大きなことばではないんですけども、まず、やはり隣にいる人。まずは2人の関係でいいと思うんですね。誰もいない、誰一人周りにいない、たった1人である孤独というのは、すごく大きな問題だと思うんですけれども。心が通じ合える人がたった1人でもいれば、もうそれで世界の見え方が全く違ってくると思います。
これは理想論過ぎますけども、それがつながっていけば、世界は変わっていくかもなという。大きなところからいろいろ何かが変わっていければ、それが一番手っ取り早いのかもしれませんけど、それは僕たちにはどうしていいか分からないことですから、隣にいる人、ごく身近にいる人との信頼で、この世界って変えられると僕は信じていますけどね。だからこんな、こんな映画ばかりというか、おぞましいこととか、とんでもないことや不穏なことが起こる映画ばかり撮っていますけども、最後、曖昧ではありますけども、僕としては一抹の希望を残して、僕の映画はいつも終わらせているつもりです。
“みんなで見る”映画の持つ力とは?
武田:今回、ベネチア国際映画祭が、新型コロナが本当に大きな流行に見舞われたイタリアで開かれて、そこでたくさんの作品が上映されて、多くの人が集まったということなんですけれども。どうなんでしょうか、そうやってみんなで集まって映画を見るということ、その意味というのは、今このコロナ禍でどういうふうに捉えていらっしゃいますか?
黒沢さん:大変だろうとは思うんですけども、僕にとってみれば、みんなで見るものこそ映画なんですね。もちろん、とはいっても今や便利な世の中で、家でDVDで見る、パソコン画面で配信で映画を見る、全然構わないです。僕もそうやって見ることが多いんですけども、それはそれ。でも、やはり本来の理想的な姿は、みんなで見る、不特定多数の人と見るということだろうと思っています。

フィルムフェスティバルのようなものは、そのことの象徴でもあろうかと思います。どうしてかというと、やっぱり映画ってすごいなと思うのは、ある何かを見て、本当に誰だか知らないほかの人と一緒に見て、みんなでわあっと笑い合う。場合によっては誰一人笑ってないけど、自分はすごくおもしろいから自分だけ笑う。また、多くの人はつまらないのか途中でぞろぞろ帰って行ったりしたけど、自分だけは、これすごくおもしろいと思ったから、エンドクレジットの最後まで残って、劇場が明るくなったら3人ぐらいしか残ってなかった。でも、その3人は君も残っていたのかって、すごく親しいように思えた。そういう、映画館で映画を見るって、ただ映画と自分の関係だけでなくて、自分とほかの人との関係まで分かってしまう。自分ってこうなんだ。映画を通して、自分ってこの社会の中でこんなポジションなんだ、みんなと一緒なんだ。あるいは、自分だけなんだ。たった3人だけど、何か共通の価値観の人がいた。そんなことが、いちいち見いだせる場所なんですね。
どんな楽しみ方をしても結構ですけども、自分はこれだ、人はこうであった。自分は人とこの点では同じであった。この点では人と違っていた。そういうことを、難しいことばとか教育システムとかを全く抜きにして、肌で直観的に感じ取れる瞬間、それがそういうエンターテインメントといいますか、娯楽、大衆娯楽の存在意義なのだろうなと僕は思いますね。
・「黒沢清監督 未公開スタジオトーク」
